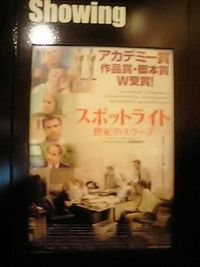2006年06月15日12:53
気持ち悪い……≫
カテゴリー │映画・演劇・その他
映画館で見逃した「ALWAYS 三丁目の夕日」をDVDで観ました。
感想を一言で言うと、「気持ち悪い」……。
感想を一言で言うと、「気持ち悪い」……。
高度成長期の東京が舞台です。あの頃は貧しかったけど人情があふれていて幸せだった、なんてのがテーマなのですが、冗談じゃない。その当時がどれだけたいへんでイヤな時代だったか。
東北から集団就職で上京してきた娘を堀北真希が演じているのですが、あんなかわいい子がいるわけがない。違う、そっちじゃない。「金の卵」なんてもてはやされていましたが、その実、劣悪な労働環境の下で低賃金で単純労働に酷使され、離職率も高かったのです。大きな希望を抱いて上京しても、苛烈な現実にボロボロにされ、絶望を胸に故郷へ帰る人は大勢いたのです。
当時は急激な都市化が進んだ頃です。それにともない多くの問題が発生しました。
国の政策で第一次産業から第二次産業への転換がなされ、多くの人口が都市に流入しました。集団就職もそうですが、これまで山村で野良仕事をしていた人やその子弟たちが生活できなくなり、都市労働者となり、満員電車に詰め込まれ「モーレツ社員」として朝から晩まで働かされました。「サラリーマンは気楽な稼業ときたもんだ」とクレイジーキャッツが歌っていましたが、当時の賃金労働者の置かれた状況の裏返しと考えるとそのときの事情がよくわかります。
映画にある町工場では、従業員の堀北を含めて家族のような一体感を持っていましたが、大企業でも、松下電器のような従業員を家族とみなす日本型経営が一般的となりました。今でこそ見直されていますが、それは雇用を保証する代わりに従業員の全生活を企業が囲い込む、佐高信が言う「社畜」化でした。
一方で離農者は増え、都市の過密と対照的に過疎化が進み、地域格差が拡大し、農村共同体が急速に崩壊しました。
その当時に社会問題となったのが、公害です。四大公害病は、映画の舞台となった年代に前後して発生しています。映画にもあった駄菓子屋で売られていたお菓子や清涼飲料水は大量の添加物が使われており、毒々しい色をしていました。
労働争議が頻発したのもこのあたりからです。エネルギー政策の転換で炭鉱労働者が職を失っていきました。女性の社会的地位も低く、結婚退職が当たり前とされていました。
この映画に描かれている時代は、決していい時代ではなかったのです。もちろん、辛い中にも楽しさがあったというのも事実です。しかしながらそれは、コインの裏表でしかありません。
映画で言うのなら、この作品が高度成長期の表であるのならば、裏側を描いた、たとえば吉永小百合の「キューポラのある街」や小津監督の「東京物語」や高倉健の「鉄道員(ぽっぽや)」(志村けんが演じた炭鉱労働者が抜群にいい)、最近ならば「嫌われ松子の一生」とセットで語られるべきです。
しかしながら、裏を見ないで高度成長期のいいところだけを取り出して「昔はよかった」というのは、日本の加害者としての近代史を「自虐的」として教えないようにしようという人たちや、韓国の悪い点だけを抜き取ってあげつらう「嫌韓厨」となんら変わりません。
しかも、クーラーを効かせた部屋で、下請け企業を絞り上げて得たボーナスで購入した、人件費が安い中国の労働者が製造したホームシアターでこのDVDを観て、「ああ、あの頃はよかった」とつぶやくのが、平成の日本の姿なのです。
これこそが、私が感じた気持ち悪さの正体です。
そうはいっても、ボロボロ泣いちゃったのですが。
ま、主張やテーマには賛同できても作品としてはカス映画もあり、その逆もあるっていう格好の例です。
どうでもいいですが、安倍晋三官房長官は会う人みんなにこの映画を薦めているのだそうです。
例によって、あの頃の日本は貧しいけれど元気だった、って。
何言うとんねん!アンタのジイサン、そのとき総理大臣だっただろう!貧しさとは無縁だっただろう!
東北から集団就職で上京してきた娘を堀北真希が演じているのですが、あんなかわいい子がいるわけがない。違う、そっちじゃない。「金の卵」なんてもてはやされていましたが、その実、劣悪な労働環境の下で低賃金で単純労働に酷使され、離職率も高かったのです。大きな希望を抱いて上京しても、苛烈な現実にボロボロにされ、絶望を胸に故郷へ帰る人は大勢いたのです。
当時は急激な都市化が進んだ頃です。それにともない多くの問題が発生しました。
国の政策で第一次産業から第二次産業への転換がなされ、多くの人口が都市に流入しました。集団就職もそうですが、これまで山村で野良仕事をしていた人やその子弟たちが生活できなくなり、都市労働者となり、満員電車に詰め込まれ「モーレツ社員」として朝から晩まで働かされました。「サラリーマンは気楽な稼業ときたもんだ」とクレイジーキャッツが歌っていましたが、当時の賃金労働者の置かれた状況の裏返しと考えるとそのときの事情がよくわかります。
映画にある町工場では、従業員の堀北を含めて家族のような一体感を持っていましたが、大企業でも、松下電器のような従業員を家族とみなす日本型経営が一般的となりました。今でこそ見直されていますが、それは雇用を保証する代わりに従業員の全生活を企業が囲い込む、佐高信が言う「社畜」化でした。
一方で離農者は増え、都市の過密と対照的に過疎化が進み、地域格差が拡大し、農村共同体が急速に崩壊しました。
その当時に社会問題となったのが、公害です。四大公害病は、映画の舞台となった年代に前後して発生しています。映画にもあった駄菓子屋で売られていたお菓子や清涼飲料水は大量の添加物が使われており、毒々しい色をしていました。
労働争議が頻発したのもこのあたりからです。エネルギー政策の転換で炭鉱労働者が職を失っていきました。女性の社会的地位も低く、結婚退職が当たり前とされていました。
この映画に描かれている時代は、決していい時代ではなかったのです。もちろん、辛い中にも楽しさがあったというのも事実です。しかしながらそれは、コインの裏表でしかありません。
映画で言うのなら、この作品が高度成長期の表であるのならば、裏側を描いた、たとえば吉永小百合の「キューポラのある街」や小津監督の「東京物語」や高倉健の「鉄道員(ぽっぽや)」(志村けんが演じた炭鉱労働者が抜群にいい)、最近ならば「嫌われ松子の一生」とセットで語られるべきです。
しかしながら、裏を見ないで高度成長期のいいところだけを取り出して「昔はよかった」というのは、日本の加害者としての近代史を「自虐的」として教えないようにしようという人たちや、韓国の悪い点だけを抜き取ってあげつらう「嫌韓厨」となんら変わりません。
しかも、クーラーを効かせた部屋で、下請け企業を絞り上げて得たボーナスで購入した、人件費が安い中国の労働者が製造したホームシアターでこのDVDを観て、「ああ、あの頃はよかった」とつぶやくのが、平成の日本の姿なのです。
これこそが、私が感じた気持ち悪さの正体です。
そうはいっても、ボロボロ泣いちゃったのですが。
ま、主張やテーマには賛同できても作品としてはカス映画もあり、その逆もあるっていう格好の例です。
どうでもいいですが、安倍晋三官房長官は会う人みんなにこの映画を薦めているのだそうです。
例によって、あの頃の日本は貧しいけれど元気だった、って。
何言うとんねん!アンタのジイサン、そのとき総理大臣だっただろう!貧しさとは無縁だっただろう!
この記事へのコメント
いやあ、さすがにツッコミどころを心得ていますなあ。
ばんばんじゃないすか。
ノスタルジイーとロマン主義はファシズムの足音と呼ばれてたと思いますが・・・
いずれにしろ、思考放棄状態の人々が多すぎます。
とまあ、愚痴を言わずに足元からがんばりましょう。
ばんばんじゃないすか。
ノスタルジイーとロマン主義はファシズムの足音と呼ばれてたと思いますが・・・
いずれにしろ、思考放棄状態の人々が多すぎます。
とまあ、愚痴を言わずに足元からがんばりましょう。
Posted by ogacci at 2006年06月15日 23:16
軍靴の音のしないファシズムですかね。
ズック靴のファシズムとか?そっちのほうが怖いような気がします。
ついでながら「和ブーム」(?)の延長にある資生堂「TSUBAKI」の「日本の女性は美しい」なんていうキャンペーンも気になります。「日本の女性」っていってもいろんな人がいるのに。パンプスの音がするファシズムでしょうか。
ズック靴のファシズムとか?そっちのほうが怖いような気がします。
ついでながら「和ブーム」(?)の延長にある資生堂「TSUBAKI」の「日本の女性は美しい」なんていうキャンペーンも気になります。「日本の女性」っていってもいろんな人がいるのに。パンプスの音がするファシズムでしょうか。
Posted by 大橋輝久 at 2006年06月16日 21:04
TSUBAKIはそうやね。資生堂は、新製品=新人キャンペーンでがんばってきたのにここへ来て、なんかブランディングの手法を変えたみたいね。とくに、椿油という伝統的な製品を、既存の中堅タレントイメージでリビルトするという感じですね。
でも、あなたの言うように、ファッションのようななだれ現象が怖いですね。
チャップリンの独裁者でも観て、来るべき日に備えるか。
でも、あなたの言うように、ファッションのようななだれ現象が怖いですね。
チャップリンの独裁者でも観て、来るべき日に備えるか。
Posted by ogacci at 2006年06月16日 22:34