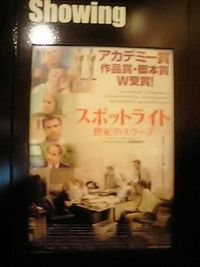2020年04月26日09:29
ポスト・コロナ時代のクラウドファンディング≫
カテゴリー │映画・演劇・その他
「クラウドファンディング(CF)」で支援したと言うと、二つの意味で驚かれます。
まず「お前そんなに金持ちなのか?」
次に「お前が寄付行為なんかするのか?」
最初の疑問ですが、私のような貧乏人でもできるCFは用意されています。
五木寛之の小説に、NYのメトロポリタン歌劇場は、財閥や大富豪だけでなく、オペラを愛する庶民が持ち寄ったわずかな金額も大事にされているとありました。
貧者の一灯は、時に巨大な影絵を壁に写します。
二つめですが、資金の一部をCFでまかなった「この世界の片隅に」(片渕須直監督・脚本)を観たことです。
エンドロールには、支援した人の名前が延々と写し出されていました。
「なんでこんな素晴らしい映画に出資しなかったんだ!」
その後悔が出発点です。
今回わずかながらCFしたのは、ミニシアター(単館系映画館)存続のキャンペーンです。大手シネコンと違い、経営基盤が脆弱で、個人経営に近いところもあります。
さらに、かける作品が一般受けしません。私は社会派作品やドキュメンタリーが好みですが、東欧や南米や中東、韓国の良作もあります。日本映画でも大手が避ける地味な作品も流します。
だから、もともと客が入らないのです。
でも、少ないながら、文化意識が高い客層ばかりです。今、ミニシアターの灯がなくなれば、文化そのものもこの地方都市から消えてしまうことを、十分にわかっています。
CFにも敏感に反応しました。私がCFした先も、目的金額を大きく超えた支援が集まっています。
CFは「何かお手伝いをしたい」との奉仕の精神が根本にあります。
エキストラで参加したい、ボランティアをやりたい、市役所やフィルム・コミッションの職員ならば地元でロケをやってほしいと「お役に立ちたい」の手段のひとつがお金です。
そこが寄付と違います。CFは製作者とのパートナーになれます。寄付は「上から目線」になりがちです。
https://motion-gallery.net/projects/minitheateraid
本来は、寄付、というか文化支援は、「国=官」が担うべきものです。
そう言うと、演劇や映画は好きでやってるし、興行だから商売だ、税金は必要はない(「私=民」)と反論があります。
演出家・劇作家の平田オリザ氏は、この二項対立を超えて「公共性」の概念を挿入し、公共性の「強い/弱い」「高い/低い」を問うべきと主張します(『芸術立国論』集英社新書、2001)。
公共性の高/低は相対的です。学校、病院、警察、消防といった、普遍的公共性を有するとされる機能も、時代や空間とともに変化します。
芸術・文化の公共性を高めようというのが、平田氏の主張と実践です。
ところが、わが日本の文化予算は先進国で最低です。
………………………………………………
令和2年度文化庁予算
1067億0900万円
……
そのうち
文化財保護など
462億9500万円(約43%)
……
芸術・芸術家支援
213億5600万円(約20%)
…………………………………………………
アベノマスク2枚
466億円(参考)
…………………………………………………
これが先進国との国際比較となると、情けなくなります。
前にも書きましたが、平田氏によると、最も国の支援が脆弱な文化・芸術に関わる人たちが、コロナ禍で真っ先に被害を受けました。
それは、昨夏の「あいちトリエンナーレ」で、いとも簡単に政治介入を受けて展示中止に追い込まれたこととも重なります。
新型コロナがどれだけ続くか。CFで一息つけても、その後どうなるか。ミニシアターはなんとかなっても、他の文化・芸術はどうか。
暗澹たる気分ですが、LGBTのサイトの編集長の合田文氏が、テレビでこんなことを話してました。
「ミニシアターの支援は、民間でなく、あくまでも国であってほしい」
「コロナの終わったその先にお金を払う。企業もその受け皿を作る」
(NHK総合「クローズアップ現代+」4月22日放送)
ポスト・コロナ時代の公共性のあり方を、官(国・政)・民(企業も)が今から考える必要があります。

https://camp-fire.jp/projects/view/256939
まず「お前そんなに金持ちなのか?」
次に「お前が寄付行為なんかするのか?」
最初の疑問ですが、私のような貧乏人でもできるCFは用意されています。
五木寛之の小説に、NYのメトロポリタン歌劇場は、財閥や大富豪だけでなく、オペラを愛する庶民が持ち寄ったわずかな金額も大事にされているとありました。
貧者の一灯は、時に巨大な影絵を壁に写します。
二つめですが、資金の一部をCFでまかなった「この世界の片隅に」(片渕須直監督・脚本)を観たことです。
エンドロールには、支援した人の名前が延々と写し出されていました。
「なんでこんな素晴らしい映画に出資しなかったんだ!」
その後悔が出発点です。
今回わずかながらCFしたのは、ミニシアター(単館系映画館)存続のキャンペーンです。大手シネコンと違い、経営基盤が脆弱で、個人経営に近いところもあります。
さらに、かける作品が一般受けしません。私は社会派作品やドキュメンタリーが好みですが、東欧や南米や中東、韓国の良作もあります。日本映画でも大手が避ける地味な作品も流します。
だから、もともと客が入らないのです。
でも、少ないながら、文化意識が高い客層ばかりです。今、ミニシアターの灯がなくなれば、文化そのものもこの地方都市から消えてしまうことを、十分にわかっています。
CFにも敏感に反応しました。私がCFした先も、目的金額を大きく超えた支援が集まっています。
CFは「何かお手伝いをしたい」との奉仕の精神が根本にあります。
エキストラで参加したい、ボランティアをやりたい、市役所やフィルム・コミッションの職員ならば地元でロケをやってほしいと「お役に立ちたい」の手段のひとつがお金です。
そこが寄付と違います。CFは製作者とのパートナーになれます。寄付は「上から目線」になりがちです。

https://motion-gallery.net/projects/minitheateraid
本来は、寄付、というか文化支援は、「国=官」が担うべきものです。
そう言うと、演劇や映画は好きでやってるし、興行だから商売だ、税金は必要はない(「私=民」)と反論があります。
演出家・劇作家の平田オリザ氏は、この二項対立を超えて「公共性」の概念を挿入し、公共性の「強い/弱い」「高い/低い」を問うべきと主張します(『芸術立国論』集英社新書、2001)。
公共性の高/低は相対的です。学校、病院、警察、消防といった、普遍的公共性を有するとされる機能も、時代や空間とともに変化します。
芸術・文化の公共性を高めようというのが、平田氏の主張と実践です。
ところが、わが日本の文化予算は先進国で最低です。
………………………………………………
令和2年度文化庁予算
1067億0900万円
……
そのうち
文化財保護など
462億9500万円(約43%)
……
芸術・芸術家支援
213億5600万円(約20%)
…………………………………………………
アベノマスク2枚
466億円(参考)
…………………………………………………
これが先進国との国際比較となると、情けなくなります。
前にも書きましたが、平田氏によると、最も国の支援が脆弱な文化・芸術に関わる人たちが、コロナ禍で真っ先に被害を受けました。
それは、昨夏の「あいちトリエンナーレ」で、いとも簡単に政治介入を受けて展示中止に追い込まれたこととも重なります。
新型コロナがどれだけ続くか。CFで一息つけても、その後どうなるか。ミニシアターはなんとかなっても、他の文化・芸術はどうか。
暗澹たる気分ですが、LGBTのサイトの編集長の合田文氏が、テレビでこんなことを話してました。
「ミニシアターの支援は、民間でなく、あくまでも国であってほしい」
「コロナの終わったその先にお金を払う。企業もその受け皿を作る」
(NHK総合「クローズアップ現代+」4月22日放送)
ポスト・コロナ時代の公共性のあり方を、官(国・政)・民(企業も)が今から考える必要があります。

https://camp-fire.jp/projects/view/256939