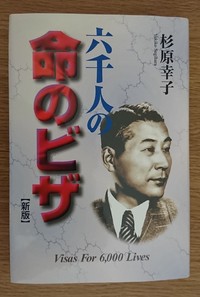2015年05月04日12:11
夢の残骸②「好き」を武器にするために≫
カテゴリー │書籍・雑誌
「好きを仕事にする」キャリア教育の怖さについて、前回は声優の大塚明夫さんの身も蓋もない本を紹介しました。
でも、好きなことにわき目も振らずに突っ走るのも若さです。ならば、好きな道を進んでしまった人はどうすればいいのか?いい本がありましたので紹介します。武蔵野音楽大学の就職課に勤務する大内孝夫さんによる『「音大卒」は武器になる』(ヤマハミュージックメディア)です。
著者は武蔵野音大で学生の就活に関わる人で、芸術系大学生のキャリアガイドなのですが、興味深いのは著者自身のキャリアで、慶應の経済学部を卒業後に富士銀行(現・みずほ銀行)に入行、証券部次長やいわき支店長などを歴任したエリート銀行マンでした。
よって本書もただのお手盛り就職本ではなく、銀行の法人担当営業マンが融資先を真剣に審査するように、就活市場での音大生のメリットや不利益を冷静にコンサルティングしていきます。
著者が記す音大生の能力のひとつは「いくら叱られてもめげない精神力」!うわぁ、パワハラへの耐性なんていやだあ、と思いますが、ブラック企業でなくても社会に出ればいくらでもあります。音大生は練習不足で30分のレッスン中ずっと怒られっぱなしだったという経験を誰もがしているそうです。
もうひとつは「コミュニケーション能力」。何だかこれも「ハイパー・メリトクラシー」の臭いが漂う言葉ですが、音大ではマンツーマンの講義が当たり前で、30~40も年上の講師とコミュニケーションを取らなくてはなりません。これは大教室での講義が主体の他大学では養えません。また音楽の知識や技術は企業内の音楽同好会などインフォーマルグループでも役に立ちます。
他にも音楽のトレーニングが人とは違う脳を育てるとか(ニセ科学のようですが……)、「礼儀」「清潔」「時間厳守」(1分でも遅れてきたらガイダンスに入れない)、「強烈なプロフェッショナル集団」であること、など。少々茶化しましたが、いずれも社会で大事な能力です。
では音大はいいことずくめなのか?いいえ。アナリストでもある著者は、音大生が真面目すぎると指摘します。ストイックに猛練習して、「楽器さえ吹ければ幸せ」と就職のことも金のことも考えず、気づいたらワーキングプア寸前という人が著者の大学の就職課にも多く訪れるようです。
なんとなく卒業した人、臨時採用や非常勤の講師をしながら正教員への道を探る人(教員免許は取れるが正教員になれるとは限らない)、この道一筋の人、モラトリアム系、ブラック企業に就職した人……。
著者はそんな音大生に、就職での「コネ」の存在を示しながら、「真面目になるより、魅力的な人間になれ!」とアドバイスを贈ります。
マンガ『のだめカンタービレ』を読んでも、プロの音楽家として自立するのは実に険しい道です。21~22歳になれば自分の実力は自ずとわかると著者は言います。有名な演奏家は十代の頃から頭角を現していますし、ソリストとして活躍する人も、プロフィールに「音大首席卒業」とあります。「才能の壁」を感じたら企業などに就職する準備をするのは挫折でもなんでもありません。著者の言葉を借りれば、
「「どのような職業につきたいか」より、「どのような人生を送りたいか」を考えよう!」
「競う音楽から楽しむ音楽へ」
です。
音大から企業に就職した著名人に、ソニー元会長の大賀典雄氏がいますし、他にも成功した人は何人もいます。同書にも武蔵野音大のOB、OGの話が出てきます。ただ、本を読んでいて、最も幸せなのは、著者本人ではないかと思いました。
前述の通り、慶大から都銀に入行したのですが、履歴書の「趣味・特技」欄に「ピアノ演奏、フルート演奏、クラシック音楽鑑賞、ショパンが好き」と書いた人で、クラシックの趣味を前面に押し出したのは同期入行の150人中で著者ひとりだったそうです。それが武蔵野音大との縁を結び、今の学生就職支援の仕事に結びついています。
また、仙台勤務のときに、地銀の幹部と音楽の話題で盛り上がり、その地銀の吹奏楽団の定期演奏会に出演したことや、別の取引先の行事で、仙台フィルの指揮もしたとあります。なんとまあうらやましい話です。
私の友人でも、吹奏楽をやっていた人が、今もアマチュア楽団でジャズを演奏しています。前回紹介した大塚明夫さんの本でも、声優に挫折した人が制作会社を経営しているとも書かれていました。好きを職業にしなくとも、人生を楽しませることは十分にできます。
後半は具体的な就活のアドバイスです。ここにも元銀行マンらしい、実践的でやや生臭い話が出てきます。音大生とは縁が薄いと思われる、「ホーソン研究」や「PDCAサイクル」などビジネス理論が出てきたり、会計学の講師をしていることもあり、音楽家が知っておくべき税務知識の基礎も掲載されています。
芸術系大学や専門学校に進もうとする人やすでに在学している人、その保護者には特におすすめです。あ、それから人事担当者も。音大卒というだけで無神経な質問をする人もいるそうですからね。
でも、好きなことにわき目も振らずに突っ走るのも若さです。ならば、好きな道を進んでしまった人はどうすればいいのか?いい本がありましたので紹介します。武蔵野音楽大学の就職課に勤務する大内孝夫さんによる『「音大卒」は武器になる』(ヤマハミュージックメディア)です。
著者は武蔵野音大で学生の就活に関わる人で、芸術系大学生のキャリアガイドなのですが、興味深いのは著者自身のキャリアで、慶應の経済学部を卒業後に富士銀行(現・みずほ銀行)に入行、証券部次長やいわき支店長などを歴任したエリート銀行マンでした。
よって本書もただのお手盛り就職本ではなく、銀行の法人担当営業マンが融資先を真剣に審査するように、就活市場での音大生のメリットや不利益を冷静にコンサルティングしていきます。
著者が記す音大生の能力のひとつは「いくら叱られてもめげない精神力」!うわぁ、パワハラへの耐性なんていやだあ、と思いますが、ブラック企業でなくても社会に出ればいくらでもあります。音大生は練習不足で30分のレッスン中ずっと怒られっぱなしだったという経験を誰もがしているそうです。
もうひとつは「コミュニケーション能力」。何だかこれも「ハイパー・メリトクラシー」の臭いが漂う言葉ですが、音大ではマンツーマンの講義が当たり前で、30~40も年上の講師とコミュニケーションを取らなくてはなりません。これは大教室での講義が主体の他大学では養えません。また音楽の知識や技術は企業内の音楽同好会などインフォーマルグループでも役に立ちます。
他にも音楽のトレーニングが人とは違う脳を育てるとか(ニセ科学のようですが……)、「礼儀」「清潔」「時間厳守」(1分でも遅れてきたらガイダンスに入れない)、「強烈なプロフェッショナル集団」であること、など。少々茶化しましたが、いずれも社会で大事な能力です。
では音大はいいことずくめなのか?いいえ。アナリストでもある著者は、音大生が真面目すぎると指摘します。ストイックに猛練習して、「楽器さえ吹ければ幸せ」と就職のことも金のことも考えず、気づいたらワーキングプア寸前という人が著者の大学の就職課にも多く訪れるようです。
なんとなく卒業した人、臨時採用や非常勤の講師をしながら正教員への道を探る人(教員免許は取れるが正教員になれるとは限らない)、この道一筋の人、モラトリアム系、ブラック企業に就職した人……。
著者はそんな音大生に、就職での「コネ」の存在を示しながら、「真面目になるより、魅力的な人間になれ!」とアドバイスを贈ります。
マンガ『のだめカンタービレ』を読んでも、プロの音楽家として自立するのは実に険しい道です。21~22歳になれば自分の実力は自ずとわかると著者は言います。有名な演奏家は十代の頃から頭角を現していますし、ソリストとして活躍する人も、プロフィールに「音大首席卒業」とあります。「才能の壁」を感じたら企業などに就職する準備をするのは挫折でもなんでもありません。著者の言葉を借りれば、
「「どのような職業につきたいか」より、「どのような人生を送りたいか」を考えよう!」
「競う音楽から楽しむ音楽へ」
です。
音大から企業に就職した著名人に、ソニー元会長の大賀典雄氏がいますし、他にも成功した人は何人もいます。同書にも武蔵野音大のOB、OGの話が出てきます。ただ、本を読んでいて、最も幸せなのは、著者本人ではないかと思いました。
前述の通り、慶大から都銀に入行したのですが、履歴書の「趣味・特技」欄に「ピアノ演奏、フルート演奏、クラシック音楽鑑賞、ショパンが好き」と書いた人で、クラシックの趣味を前面に押し出したのは同期入行の150人中で著者ひとりだったそうです。それが武蔵野音大との縁を結び、今の学生就職支援の仕事に結びついています。
また、仙台勤務のときに、地銀の幹部と音楽の話題で盛り上がり、その地銀の吹奏楽団の定期演奏会に出演したことや、別の取引先の行事で、仙台フィルの指揮もしたとあります。なんとまあうらやましい話です。
私の友人でも、吹奏楽をやっていた人が、今もアマチュア楽団でジャズを演奏しています。前回紹介した大塚明夫さんの本でも、声優に挫折した人が制作会社を経営しているとも書かれていました。好きを職業にしなくとも、人生を楽しませることは十分にできます。
後半は具体的な就活のアドバイスです。ここにも元銀行マンらしい、実践的でやや生臭い話が出てきます。音大生とは縁が薄いと思われる、「ホーソン研究」や「PDCAサイクル」などビジネス理論が出てきたり、会計学の講師をしていることもあり、音楽家が知っておくべき税務知識の基礎も掲載されています。
芸術系大学や専門学校に進もうとする人やすでに在学している人、その保護者には特におすすめです。あ、それから人事担当者も。音大卒というだけで無神経な質問をする人もいるそうですからね。
この記事へのコメント
大変興味深い記事をありがとう。
丁度先週に武蔵野音大卒と東大卒の二人の音楽家と公演を行ったのでタイムリーな内容でした。
ところで、今の武蔵野音大はかつての名声からは遠ざかっているようです。少子化でどの音大も優秀な新入生を確保するのに大変なようです。因に、これは愛知県芸卒から先月聞いたお話です。
丁度先週に武蔵野音大卒と東大卒の二人の音楽家と公演を行ったのでタイムリーな内容でした。
ところで、今の武蔵野音大はかつての名声からは遠ざかっているようです。少子化でどの音大も優秀な新入生を確保するのに大変なようです。因に、これは愛知県芸卒から先月聞いたお話です。
Posted by tomiyama at 2015年05月06日 04:07
おお、お久しぶりです。
優秀な人材を囲い込むみたいで、なんだか甲子園常連校の野球部のようですね。
でも学校も背に腹は代えられないみたいで、武蔵野音大もキャンパスを大改装すると同書にありました。
南河内芸術大学(仮名)も昔とかなり違うみたいです。
優秀な人材を囲い込むみたいで、なんだか甲子園常連校の野球部のようですね。
でも学校も背に腹は代えられないみたいで、武蔵野音大もキャンパスを大改装すると同書にありました。
南河内芸術大学(仮名)も昔とかなり違うみたいです。
Posted by 大橋輝久 at 2015年05月06日 07:32
at 2015年05月06日 07:32
 at 2015年05月06日 07:32
at 2015年05月06日 07:32著者の大内です。過分な書評ありがとうございます。社会で通用するには本当に差別化された高度な技能や能力であれば他を抜きん出てトップを目指せますが、ほとんどの人はドングリの背比べ。かくいう私も同様で若い頃、並み居る同期に追いついていくには、自ら進んでの多大な労働時間の提供と地に這うようなドブ板精神しかありませんでした。そういう中で私自身に必要だったのが「めげない精神力」だったのですが、最近の若い人の多くに不足する力だと支店長時代に思っていました。武蔵野にお世話になり、それを多くの音大生が身に付けていることは驚きでしたし、そのような彼らが生きる道は色々あることを伝えたいと思いました。私の考えが少しでもみなさんの参考になれば幸いです。ありがとうございました。
Posted by 大内 孝夫 at 2015年05月15日 03:30
こちらこそ拙い文章を目に留めていただきありがとうございます。
私もかつて、ある芸術系大学で夢見る学生でした。選んだ道に悔いはないとは言え、費やした貴重な時間やお金や必要のない苦労を考えると、どうしても老婆心ながら一言物申したくもなります。
そんなときに大内さんのような、酸いも甘いも噛み分けた方が学生の近くでアドバイスをしてくれたらと、ご高著を拝読して思った次第です。
そうは申しましても、若者、特に芸術系の学校に進む人は大人の意見などに耳を貸さなかったりします。それくらいでなければ大成しないのでしょう。自らを省みても難しいところです。
学生の青春の浪費や搾取を防ぐためにも、就職支援やご講義などさらなるご活躍をお祈り申し上げます。
私もかつて、ある芸術系大学で夢見る学生でした。選んだ道に悔いはないとは言え、費やした貴重な時間やお金や必要のない苦労を考えると、どうしても老婆心ながら一言物申したくもなります。
そんなときに大内さんのような、酸いも甘いも噛み分けた方が学生の近くでアドバイスをしてくれたらと、ご高著を拝読して思った次第です。
そうは申しましても、若者、特に芸術系の学校に進む人は大人の意見などに耳を貸さなかったりします。それくらいでなければ大成しないのでしょう。自らを省みても難しいところです。
学生の青春の浪費や搾取を防ぐためにも、就職支援やご講義などさらなるご活躍をお祈り申し上げます。
Posted by 大橋輝久 at 2015年05月15日 11:39
at 2015年05月15日 11:39
 at 2015年05月15日 11:39
at 2015年05月15日 11:39