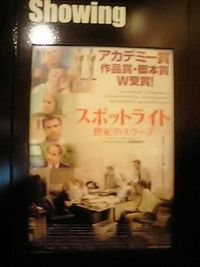2012年10月28日06:57
死を想え≫
カテゴリー │映画・演劇・その他
周防正行監督の映画「終の信託」を観てきました。尊厳死をテーマにした映画です。
ストーリーは、余命いくばくもないことを悟った中年患者(役所広司)が、女性医師(草刈民代)に、自分の終末医療を託します。
医師はその少し前に、痛々しい経験をしています。そのことから、延命治療を止めます。ところが話はそう簡単にはいきません。彼女は患者に薬物を投与し、積極的安楽死を行います。
それから時間が過ぎ、医師は殺人罪で検察庁に呼び出されます。
医師の行為は殺人だと検察官(大沢たかお)は迫り、医師は医療行為だと主張します。
という映画なのですが……。
私は非常に、強く、失望したのです。
あまりにもテーマの描写が薄っぺら過ぎます。
並の映画だったらそこまで言いませんよ。
でも、あの周防正行監督です。
「Shall we ダンス?」で中年男性の微妙な内面をコミカルに描き、「それでもボクはやってない」で一転、痴漢冤罪の社会派映画を撮って話題になった、あの周防監督です。もっと深く描くことはできたはずなのです。
そりゃ、いいところもありますよ。前半部分の静かな大人の愛(恋愛、とはまた違う)から一転して、後半部分の検事と医師の会話劇は緊張感あふれるもので、役者の緊迫感のある演技は論題を深めるために最適のものでした。
議論をケンカと完全に勘違いしている橋下大阪市長の顔にうんざりしていた私にとって、これこそ論争だというもので、l映画ではなく舞台でやったらまた別の味わいが出るのではと観ながら思いました。
また、監督は、このテーマを広く訴えるために、あえて議論の底を浅くして一般向けにしたのでは、とも憶測しました。
それにしても、もっと撮り方はあっただろう、と、深い失望と残念感を抱きながら映画館を後にしたのでした。
映画の質は置いといて、作中で医師が行った行為は、完全に落ち度があって、法律家でなくとも賛同できないものでした。
詳しくは映画を観ていただきたいのですが、医師は患者に踏み込み過ぎ、共依存関係になってしまいました。次にリビング・ウィルを正式な書面で行わせなかったこと、家族への説明を促さなかったことで誤解を招くことになりました。そして過去の安楽死の判例を踏まえなかったこと。
映画にもすべて出てきますし、素人の私ですら知っていたことです。それをしなかったことは、プロの医師として失格以前です。
はっきり言って、医師に同情するところなどなく、話にもなりません。
私事ですが、数年前の身内の闘病や看取りを通じて、死や宗教について、それなりに考えるようになってきました。
社会的にも、死が大きなテーマになってきました。
少子高齢化社会で、介護や終末医療の問題が多く語られるようになりました。一昨年の流行語にもなった「無縁社会」、昨年の東日本大震災など、避けて通らなくてはならない認識だった死が、身近なものとなりました。
最近でしたら、若くして亡くなった流通ジャーナリストの金子哲雄さんが遺した「挨拶」が見事な「終活」だったと話題になりました。
また、自民党の総裁選挙に出馬した石原伸晃前幹事長がニュース番組で尊厳死について言及しました。本人の真意とはかなり誤解されて伝わったようですが、真剣に議論されてしかるべき問題です。
エンタテインメントの世界でも、死について取り扱った良作があります。映画でしたら砂田麻美監督が父の「終活」を涙と笑いで追ったドキュメンタリー「エンディングノート」、アメリカでしたらユアン・マクレガー主演の「人生はビギナーズ」などを最近観ました。
お涙頂戴の難病モノでも、盛り上げるためのホラーやスプラッターでもなく、死を真正面からテーマにする作品が増えてきたことをうれしく思っています。
死を想え。そして死を語れ。それが昔からの私の変わらぬ主張です。
なぜならば、死を考えることは、生きることを考えることだからです。
そう言う私はエンディングノートを購入して早2年、ひと文字も書けていないのですが……。
ストーリーは、余命いくばくもないことを悟った中年患者(役所広司)が、女性医師(草刈民代)に、自分の終末医療を託します。
医師はその少し前に、痛々しい経験をしています。そのことから、延命治療を止めます。ところが話はそう簡単にはいきません。彼女は患者に薬物を投与し、積極的安楽死を行います。
それから時間が過ぎ、医師は殺人罪で検察庁に呼び出されます。
医師の行為は殺人だと検察官(大沢たかお)は迫り、医師は医療行為だと主張します。
という映画なのですが……。
私は非常に、強く、失望したのです。
あまりにもテーマの描写が薄っぺら過ぎます。
並の映画だったらそこまで言いませんよ。
でも、あの周防正行監督です。
「Shall we ダンス?」で中年男性の微妙な内面をコミカルに描き、「それでもボクはやってない」で一転、痴漢冤罪の社会派映画を撮って話題になった、あの周防監督です。もっと深く描くことはできたはずなのです。
そりゃ、いいところもありますよ。前半部分の静かな大人の愛(恋愛、とはまた違う)から一転して、後半部分の検事と医師の会話劇は緊張感あふれるもので、役者の緊迫感のある演技は論題を深めるために最適のものでした。
議論をケンカと完全に勘違いしている橋下大阪市長の顔にうんざりしていた私にとって、これこそ論争だというもので、l映画ではなく舞台でやったらまた別の味わいが出るのではと観ながら思いました。
また、監督は、このテーマを広く訴えるために、あえて議論の底を浅くして一般向けにしたのでは、とも憶測しました。
それにしても、もっと撮り方はあっただろう、と、深い失望と残念感を抱きながら映画館を後にしたのでした。
映画の質は置いといて、作中で医師が行った行為は、完全に落ち度があって、法律家でなくとも賛同できないものでした。
詳しくは映画を観ていただきたいのですが、医師は患者に踏み込み過ぎ、共依存関係になってしまいました。次にリビング・ウィルを正式な書面で行わせなかったこと、家族への説明を促さなかったことで誤解を招くことになりました。そして過去の安楽死の判例を踏まえなかったこと。
映画にもすべて出てきますし、素人の私ですら知っていたことです。それをしなかったことは、プロの医師として失格以前です。
はっきり言って、医師に同情するところなどなく、話にもなりません。
私事ですが、数年前の身内の闘病や看取りを通じて、死や宗教について、それなりに考えるようになってきました。
社会的にも、死が大きなテーマになってきました。
少子高齢化社会で、介護や終末医療の問題が多く語られるようになりました。一昨年の流行語にもなった「無縁社会」、昨年の東日本大震災など、避けて通らなくてはならない認識だった死が、身近なものとなりました。
最近でしたら、若くして亡くなった流通ジャーナリストの金子哲雄さんが遺した「挨拶」が見事な「終活」だったと話題になりました。
また、自民党の総裁選挙に出馬した石原伸晃前幹事長がニュース番組で尊厳死について言及しました。本人の真意とはかなり誤解されて伝わったようですが、真剣に議論されてしかるべき問題です。
エンタテインメントの世界でも、死について取り扱った良作があります。映画でしたら砂田麻美監督が父の「終活」を涙と笑いで追ったドキュメンタリー「エンディングノート」、アメリカでしたらユアン・マクレガー主演の「人生はビギナーズ」などを最近観ました。
お涙頂戴の難病モノでも、盛り上げるためのホラーやスプラッターでもなく、死を真正面からテーマにする作品が増えてきたことをうれしく思っています。
死を想え。そして死を語れ。それが昔からの私の変わらぬ主張です。
なぜならば、死を考えることは、生きることを考えることだからです。
そう言う私はエンディングノートを購入して早2年、ひと文字も書けていないのですが……。