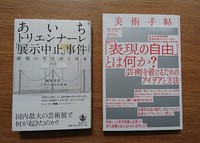2014年03月31日11:17
「笑っていいとも!」と〈大衆〉の終わり≫
カテゴリー │放送
我が家には私が5歳くらいのときに描いたタモリの絵が残っています。広告の裏にクレヨンで描いた落書きですが、母親が捨てずに取っておいたものです。今もどこかにあるはずです。ポマードで固めた髪に眼帯(サングラスではない時代です)、タキシード姿、ハンドマイクを持っていたと記憶しています。
当時のタモリは大人の世界の住民で、子どもが安易に近づいてはいけない、タブー感が漂っていました。エッチな話もそうですが、「今夜は最高!」などで魅せるジャズ演奏は、18歳未満お断りの、まさに大人の遊び場でした。
「いいとも!」が始まったのが1982年。まだその頃は「お茶の間」という言葉が健在でした。確か田中康夫や景山民夫、山本晋也といった「マルチタレント」が出演していました。後に嵐山光三郎、志茂田景樹らも出演しました。「ニューアカ」ブームのような、知的に戯れるゲームの空気がありました。
1985年、広告代理店の博報堂のシンクタンク「博報堂生活総合研究所」が「分衆の誕生」というリポートを出版し、「大衆から分衆へ」と言われるようになりました。我が家でもテレビが2台、3台と増え、両親、弟、私がそれぞれの個室で違う番組を同時間帯に観るようになりました。
学校でも同じクラスの中でなんとなくの親しいグループに分かれるようになりました。仲が悪いわけではないのですが、スポーツ系(リア充系)、サブカル系(オタク系)、ヤンキー系、ガリ勉系など、趣味や好みなどで固まるようになりました(今で言えば「トライブ」か「クラスタ」でしょうか)。ただ、完全に分かれていたのではありませんでした。グループ間の媒介となったのは、やっぱりテレビ番組でした。
同時代的なテレビ番組というのがありました。私の団塊ジュニア世代では「全員集合!」→「ひょうきん族」→「元気が出るテレビ」「ねるとん紅鯨団」「イカ天」あたりでしょうか。ただ、全世代的に観ており、共通の話題になったのが、「いいとも!」でした。
「いいとも!」以外のテレビ番組が大衆娯楽(というより話のネタ)のシンボリックな存在でなくなったのは、テレビそのものが観られなくなったということもあります。別のところで記したのですが、美容院で美容師さんと話を合わせようとして、テレビに出ている人気タレントの話を振ったら、美容師のお姉さんはほとんどテレビを観てなくて、会話が成り立たなかったということがありました。同じようなことは、職場の大学生アルバイトとの間にもありました。
理由として、多メディア化、娯楽の多様化といったことが原因として上げられます。NHK放送文化研究所が5年ごとに行う「国民生活時間調査」によれば、特に若い世代でテレビ離れが著しく見られます。2010年の調査では20代男性の20%が一度もテレビを視聴しないとの結果が出ました。若い社会人の多忙さもあるでしょうが、趣味や娯楽のタコツボ化が起こっていることでしょう。
ただ、「いいとも!」だけは誰とも共通言語として通用しました。他の長寿番組と違い、「いいとも!」だけは何となく話が合いました。
「いいとも!」そのものも32年間で変容しました。不自然なタイアップがほとんどになったり、かつてはトンガってた企画も無難なものになり、視聴者にすり寄ったものになりました。出演者も、どこのチャンネルでも見られるお笑い芸人や、知的さを光らせる「マルチタレント」とは全然違う、知的さを提供し消費させる「タレント文化人」になってしまい、一時は大衆にすり寄ってばかりの予定調和の番組でした。
それは逆説的に、テレビの「クールなメディア」、すなわち視聴者が文句を言うためのツールとして機能していたとも言えます。
これは多分、タモリ自身も感じてたことでしょう。自分とスタッフだけが楽しければいいという「タモリ倶楽部」や「ブラタモリ」のほうが好きだという人が多いのもわかります。やっぱりテレビは大衆のためにあるものだと「いいとも!」を振り返って思います。
大衆のほうに変容が見られたのは、お笑いへのまなざしが鋭くなったことです。かつては「タモリ・たけし・さんま」のいわゆる「BIG3」は、テレビ低俗論の代名詞のようなものでした。特に「ひょうきん族」のようなおふざけとハプニング(すなわちそれがテレビ的ということですが)は、年配の人から毛嫌いされてきました。私も年配で立場のある人から「たけしのような……」「さんまみたいな……」との罵倒を何度も聞かされました。
ところが、今はお笑い芸人は大人気です。これまでならば俳優養成所やアイドルの事務所の門を叩いた人が、お笑いの道を志します。お笑いの事務所付属の学校は門前に市を成しています。若手芸人のお笑いライブは大人気だそうです。
そして、お笑いは実は頭が良くなければできないことも知っています。与太郎キャラの木久扇も、アホを演じる坂田利夫も、本当は賢いことを見抜いています。その頂点が、「BIG3」です。タモリがクレバーなことを、今や誰も疑いません。マスコミ業界以外の普通の人も、呼び方が「タモリ」→「タモリさん」→「タモさん」と変わってきました。32年のうちに大衆が成熟したということでしょう。
そう祭り上げられて忸怩たる思いだったのが、実はタモリ自身だったのかもしれません。本人はまだ全裸で赤塚不二雄とSMショーをやっていたいのかもしれません。
いずれにせよ、今日で「いいとも!」が終わります。終了後はどうなるのでしょうか?ひとつだけ確実に言えるのは、日本人がなんとなく共有してきた大衆文化がなくなることです。それは真の意味で〈大衆〉の終焉を意味するのでしょう。
かつて日本人は、祝日には軒先に日の丸の旗を出し、毎朝神棚や仏壇に手を合わせるのが自然とされていました。「いいとも!」も日の丸や神仏と同じく、普遍的価値として抱かれてきた象徴的存在としてあり、そして今日を境に忘れられていくのでしょう。
〈大衆〉が明日から〈分衆〉や〈微衆〉になる。そんなことを思いながら最後の「いいとも!」を観ようと思います。

当時のタモリは大人の世界の住民で、子どもが安易に近づいてはいけない、タブー感が漂っていました。エッチな話もそうですが、「今夜は最高!」などで魅せるジャズ演奏は、18歳未満お断りの、まさに大人の遊び場でした。
「いいとも!」が始まったのが1982年。まだその頃は「お茶の間」という言葉が健在でした。確か田中康夫や景山民夫、山本晋也といった「マルチタレント」が出演していました。後に嵐山光三郎、志茂田景樹らも出演しました。「ニューアカ」ブームのような、知的に戯れるゲームの空気がありました。
1985年、広告代理店の博報堂のシンクタンク「博報堂生活総合研究所」が「分衆の誕生」というリポートを出版し、「大衆から分衆へ」と言われるようになりました。我が家でもテレビが2台、3台と増え、両親、弟、私がそれぞれの個室で違う番組を同時間帯に観るようになりました。
学校でも同じクラスの中でなんとなくの親しいグループに分かれるようになりました。仲が悪いわけではないのですが、スポーツ系(リア充系)、サブカル系(オタク系)、ヤンキー系、ガリ勉系など、趣味や好みなどで固まるようになりました(今で言えば「トライブ」か「クラスタ」でしょうか)。ただ、完全に分かれていたのではありませんでした。グループ間の媒介となったのは、やっぱりテレビ番組でした。
同時代的なテレビ番組というのがありました。私の団塊ジュニア世代では「全員集合!」→「ひょうきん族」→「元気が出るテレビ」「ねるとん紅鯨団」「イカ天」あたりでしょうか。ただ、全世代的に観ており、共通の話題になったのが、「いいとも!」でした。
「いいとも!」以外のテレビ番組が大衆娯楽(というより話のネタ)のシンボリックな存在でなくなったのは、テレビそのものが観られなくなったということもあります。別のところで記したのですが、美容院で美容師さんと話を合わせようとして、テレビに出ている人気タレントの話を振ったら、美容師のお姉さんはほとんどテレビを観てなくて、会話が成り立たなかったということがありました。同じようなことは、職場の大学生アルバイトとの間にもありました。
理由として、多メディア化、娯楽の多様化といったことが原因として上げられます。NHK放送文化研究所が5年ごとに行う「国民生活時間調査」によれば、特に若い世代でテレビ離れが著しく見られます。2010年の調査では20代男性の20%が一度もテレビを視聴しないとの結果が出ました。若い社会人の多忙さもあるでしょうが、趣味や娯楽のタコツボ化が起こっていることでしょう。
ただ、「いいとも!」だけは誰とも共通言語として通用しました。他の長寿番組と違い、「いいとも!」だけは何となく話が合いました。
「いいとも!」そのものも32年間で変容しました。不自然なタイアップがほとんどになったり、かつてはトンガってた企画も無難なものになり、視聴者にすり寄ったものになりました。出演者も、どこのチャンネルでも見られるお笑い芸人や、知的さを光らせる「マルチタレント」とは全然違う、知的さを提供し消費させる「タレント文化人」になってしまい、一時は大衆にすり寄ってばかりの予定調和の番組でした。
それは逆説的に、テレビの「クールなメディア」、すなわち視聴者が文句を言うためのツールとして機能していたとも言えます。
これは多分、タモリ自身も感じてたことでしょう。自分とスタッフだけが楽しければいいという「タモリ倶楽部」や「ブラタモリ」のほうが好きだという人が多いのもわかります。やっぱりテレビは大衆のためにあるものだと「いいとも!」を振り返って思います。
大衆のほうに変容が見られたのは、お笑いへのまなざしが鋭くなったことです。かつては「タモリ・たけし・さんま」のいわゆる「BIG3」は、テレビ低俗論の代名詞のようなものでした。特に「ひょうきん族」のようなおふざけとハプニング(すなわちそれがテレビ的ということですが)は、年配の人から毛嫌いされてきました。私も年配で立場のある人から「たけしのような……」「さんまみたいな……」との罵倒を何度も聞かされました。
ところが、今はお笑い芸人は大人気です。これまでならば俳優養成所やアイドルの事務所の門を叩いた人が、お笑いの道を志します。お笑いの事務所付属の学校は門前に市を成しています。若手芸人のお笑いライブは大人気だそうです。
そして、お笑いは実は頭が良くなければできないことも知っています。与太郎キャラの木久扇も、アホを演じる坂田利夫も、本当は賢いことを見抜いています。その頂点が、「BIG3」です。タモリがクレバーなことを、今や誰も疑いません。マスコミ業界以外の普通の人も、呼び方が「タモリ」→「タモリさん」→「タモさん」と変わってきました。32年のうちに大衆が成熟したということでしょう。
そう祭り上げられて忸怩たる思いだったのが、実はタモリ自身だったのかもしれません。本人はまだ全裸で赤塚不二雄とSMショーをやっていたいのかもしれません。
いずれにせよ、今日で「いいとも!」が終わります。終了後はどうなるのでしょうか?ひとつだけ確実に言えるのは、日本人がなんとなく共有してきた大衆文化がなくなることです。それは真の意味で〈大衆〉の終焉を意味するのでしょう。
かつて日本人は、祝日には軒先に日の丸の旗を出し、毎朝神棚や仏壇に手を合わせるのが自然とされていました。「いいとも!」も日の丸や神仏と同じく、普遍的価値として抱かれてきた象徴的存在としてあり、そして今日を境に忘れられていくのでしょう。
〈大衆〉が明日から〈分衆〉や〈微衆〉になる。そんなことを思いながら最後の「いいとも!」を観ようと思います。