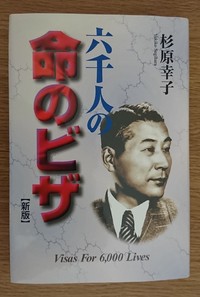2010年02月08日13:02
昨日のコメントへの答え≫
カテゴリー │書籍・雑誌
文学談義は大好きなのですが、まったく予想外のところから批判の矢が飛んできました。前回書いた五木寛之『親鸞』と、五木先生の講演の件です。
とりあえずコメントを読んでみてください。本筋とは関係ないので無視してもいいのですが、私は一応「誠実」なので、お答えいたします。
①②「何様ですか」との問いですが、一応、大学時代に階層研究をかじっていた者です。ですからイベントや映画などの聴衆層には敏感になります。服装だけでなく、言葉遣い、立ち振る舞いなど。詳しくはフランスの社会学者ブルデューらの研究を参考にしてほしいのですが、私の見た限り、会場には上品な仕立てのスーツを着た人や文学や仏教についての教養ある会話をしていた人は見かけませんでした(同様に、二十歳代の人も見られませんでした)。
私は2階席におり、周囲は私の家の近所のおじさん、おばさん、親戚の人たちと同程度の、いわゆる庶民階層と思われる人たちでした。1階席はわかりませんが、たぶん、同じでしょう。もし違うというのならば、データを提示した上で再反論してください。
そんな私のリポートを不愉快と感じられたとのことですが、実は階層研究は長期にわたってタブー視されてきました。「格差社会」などと声高に言われ始めたのはほんの10年に満たない時期です。ですから、人はみな平等だという戦後民主主義下では、研究そのものが一般に受け入れられませんでした。論者は団塊世代とのことですから、不快に思われても不思議はありません。
しかしながら、私は、逆のことを思います。庶民階級の人たちが、高名な作家の講演を聴きに詰めかけることは、この国の文化的民度が極めて高いことを示していることで、素晴らしいことではないか、と。
もちろん、野次馬やミーハー精神の人もいたことでしょう。テレビ文化人だろうがお笑い芸人だろうがジャニーズのアイドルだろうが、有名人に会うというだけで満足する人もいます。ただ、五木先生の講演会はそれとは大分異なりました。今の流行作家ならばともかく、800年も前の坊さんのことを書いた人に、しかも金を払ってまで話を聞きたいというのは、タレントを見たいという感情とはかなり違うものだと思われます。
そこまでの文化的精神を、これまた失礼ながら、庶民階層(この言葉が嫌ならば「普通の生活をしている人たち」と言い換えてもいいでしょう。麻生前総理や鳩山首相夫妻のような名家の出身者以外という意味です)の人々が持ち、知識を得、教養を磨きたいと思っていることは、怒ることではなく、喜ばしいことではないのでしょうか。
五木先生は講演で、仏陀やキリストや蓮如らの例を出しながら、語ることの大切さを話されました。小説の中の親鸞がそうでした。当時の最高権威である比叡山での出世栄達や、皇族や公家たちを相手に派手な法会をする栄誉を捨て、民衆や下賤とされた人たちの中に入っていき、説法をし、問答します。物語の中でしか知りませんが、表層的な権威や名誉よりも、名もなき庶民を大切にされた親鸞に、私は五木先生の姿を重ねます。
テレビで一見庶民的なコメンテーターに見える文化人の中には、芸能プロダクションに所属していて、講演で高額の謝礼を取る人もいます。また、著名な評論家の講演を聞ける人は、地方の商工団体に加盟している経営者だけだったりすることもあります。
そんな事例をいくつか知っているだけに、金持ちでも名士でもない、普通に生活を営む庶民と五木先生が交わり話を聞ける機会は、不愉快どころか素晴らしいことだと思うのです。
③江原啓之や勝間和代の件は、当事者や関係者以外にはわかりにくいところでしょう。ただ、わかる人にはものすごくわかってもらえると思っています。
かつて、五木先生のサイン会にお邪魔したことがあります。『四季・亜紀子』の刊行記念のときでした。私も大ファンで、短い時間でしたがいろいろとお話をさせていただきました。その会場で、ただのファンの私とはまったく別次元で、真剣なまなざしをした女性が何人かいました。
当時は「こころの時代」などと呼ばれ、自己啓発本や精神科医の書いた本がよく売れていました。五木先生も『蓮如』や『大河の一滴』『他力』など、宗教や、ともすればスピリチュアルに分類されるようなベストセラーを書かれていました。
サイン会で先生を見つめる目は、新興宗教のグルを見つめるような、すがるような目つきでした。別にその人だけがおかしいわけではありません。その時代は、社会不安が増大し、なにかにすがるような人がたくさんいました。それはITだったり、金融工学だったり、身体改造だったり、わが国の誇れる歴史だったり、様々でした。サイン会に来ていた中年の女性は、それがたまたま五木先生だったというだけでしょう。
その頃はまだラジオ番組「五木寛之の夜」が放送されていました。ラジオの力は偉大で、パーソナリティを神格化させます。ある有名なメディア研究者は、ラジオよりテレビが先に登場していたら、ヒトラーはたちまち姿を消していたとさえ言います。サイン会で見た女性は、やはり五木先生のラジオの熱心な聴取者でした。
あれから10年が経ちました。社会の至る所でほころびが目立ち始めました。パソコンの前に座って株取引をするだけで大儲けする人もいれば、ネットカフェ難民やワーキングプアなどという言葉も生まれました。ここまで生きにくい世の中なのだから、何かにすがりつきたくなるのは当然です。そのうちの一つが小泉首相であり、もうひとつが、江原啓之氏に代表されるスピリチュアル・ブームです。
江原氏の講演会はたいへんな人気だそうです。今ではブームは過ぎたと言われます。たしかに、テレビで見ることは少なくなりました。でも、若い女性たちの間ではまだスピリチュアルは廃れていません。日本国内の「パワースポット」には行列ができているとの話です。つい最近も、若い人気歌手とお笑いタレントが、わざわざアメリカのパワースポットに行っていたとワイドショーで話題になっていました。
江原氏に代わってここ数年人気になっているのが、勝間和代氏です。「カツマー」なんて呼ばれる熱心なファンが多くいることも知られています。確実な論拠はありませんが、江原氏の講演に詰め掛けた人たちが、勝間氏に流れたのではないかと考えています。結局、なにかにすがりたいとの思いは同じでしょう。それゆえ、精神科医の香山リカ氏が「<勝間和代>を目指さない」と警鐘を鳴らした本がベストセラーになり、ちょっとした議論になりました。
私は、10年前、五木先生を凝視していた女性の目を忘れることはできません。おそらく、江原啓之氏の講演では、あの目をした人たちが演壇を熱いまなざしで見つめていたのでしょう。江原氏だけではなく、若い女性向けのセミナーでは、とにかく何かを得ようとか、何かを摑もうというヒリヒリとした痛々しさがあるそうです。それは、時代の大変さと、そのなかで女性が置かれた厳しい立場を物語っています。
幸い、五木先生の講演会では、そのような重い空気はありませんでした。もし江原啓之氏や勝間和代氏らに向けられるような、何者かにすがる空気では、私は耐えられなかったでしょう。それはつまり、すこしは空気が弛緩していたからだとも言えますし、主な客層が中高年から高齢者だったからとも考えられます。
ただ、単純に、よかったよかったでは済まされないでしょう。おそらく別の講演会やセミナーでは、10年前よりもさらに厳しい視線が一斉に演壇に注がれでいたでしょうから。
以上、いただいたコメントへの私からの答えです。
今度はまともな文学議論をしたいものですね。こんな枝葉末節や揚げ足取りではなく。
とりあえずコメントを読んでみてください。本筋とは関係ないので無視してもいいのですが、私は一応「誠実」なので、お答えいたします。
①②「何様ですか」との問いですが、一応、大学時代に階層研究をかじっていた者です。ですからイベントや映画などの聴衆層には敏感になります。服装だけでなく、言葉遣い、立ち振る舞いなど。詳しくはフランスの社会学者ブルデューらの研究を参考にしてほしいのですが、私の見た限り、会場には上品な仕立てのスーツを着た人や文学や仏教についての教養ある会話をしていた人は見かけませんでした(同様に、二十歳代の人も見られませんでした)。
私は2階席におり、周囲は私の家の近所のおじさん、おばさん、親戚の人たちと同程度の、いわゆる庶民階層と思われる人たちでした。1階席はわかりませんが、たぶん、同じでしょう。もし違うというのならば、データを提示した上で再反論してください。
そんな私のリポートを不愉快と感じられたとのことですが、実は階層研究は長期にわたってタブー視されてきました。「格差社会」などと声高に言われ始めたのはほんの10年に満たない時期です。ですから、人はみな平等だという戦後民主主義下では、研究そのものが一般に受け入れられませんでした。論者は団塊世代とのことですから、不快に思われても不思議はありません。
しかしながら、私は、逆のことを思います。庶民階級の人たちが、高名な作家の講演を聴きに詰めかけることは、この国の文化的民度が極めて高いことを示していることで、素晴らしいことではないか、と。
もちろん、野次馬やミーハー精神の人もいたことでしょう。テレビ文化人だろうがお笑い芸人だろうがジャニーズのアイドルだろうが、有名人に会うというだけで満足する人もいます。ただ、五木先生の講演会はそれとは大分異なりました。今の流行作家ならばともかく、800年も前の坊さんのことを書いた人に、しかも金を払ってまで話を聞きたいというのは、タレントを見たいという感情とはかなり違うものだと思われます。
そこまでの文化的精神を、これまた失礼ながら、庶民階層(この言葉が嫌ならば「普通の生活をしている人たち」と言い換えてもいいでしょう。麻生前総理や鳩山首相夫妻のような名家の出身者以外という意味です)の人々が持ち、知識を得、教養を磨きたいと思っていることは、怒ることではなく、喜ばしいことではないのでしょうか。
五木先生は講演で、仏陀やキリストや蓮如らの例を出しながら、語ることの大切さを話されました。小説の中の親鸞がそうでした。当時の最高権威である比叡山での出世栄達や、皇族や公家たちを相手に派手な法会をする栄誉を捨て、民衆や下賤とされた人たちの中に入っていき、説法をし、問答します。物語の中でしか知りませんが、表層的な権威や名誉よりも、名もなき庶民を大切にされた親鸞に、私は五木先生の姿を重ねます。
テレビで一見庶民的なコメンテーターに見える文化人の中には、芸能プロダクションに所属していて、講演で高額の謝礼を取る人もいます。また、著名な評論家の講演を聞ける人は、地方の商工団体に加盟している経営者だけだったりすることもあります。
そんな事例をいくつか知っているだけに、金持ちでも名士でもない、普通に生活を営む庶民と五木先生が交わり話を聞ける機会は、不愉快どころか素晴らしいことだと思うのです。
③江原啓之や勝間和代の件は、当事者や関係者以外にはわかりにくいところでしょう。ただ、わかる人にはものすごくわかってもらえると思っています。
かつて、五木先生のサイン会にお邪魔したことがあります。『四季・亜紀子』の刊行記念のときでした。私も大ファンで、短い時間でしたがいろいろとお話をさせていただきました。その会場で、ただのファンの私とはまったく別次元で、真剣なまなざしをした女性が何人かいました。
当時は「こころの時代」などと呼ばれ、自己啓発本や精神科医の書いた本がよく売れていました。五木先生も『蓮如』や『大河の一滴』『他力』など、宗教や、ともすればスピリチュアルに分類されるようなベストセラーを書かれていました。
サイン会で先生を見つめる目は、新興宗教のグルを見つめるような、すがるような目つきでした。別にその人だけがおかしいわけではありません。その時代は、社会不安が増大し、なにかにすがるような人がたくさんいました。それはITだったり、金融工学だったり、身体改造だったり、わが国の誇れる歴史だったり、様々でした。サイン会に来ていた中年の女性は、それがたまたま五木先生だったというだけでしょう。
その頃はまだラジオ番組「五木寛之の夜」が放送されていました。ラジオの力は偉大で、パーソナリティを神格化させます。ある有名なメディア研究者は、ラジオよりテレビが先に登場していたら、ヒトラーはたちまち姿を消していたとさえ言います。サイン会で見た女性は、やはり五木先生のラジオの熱心な聴取者でした。
あれから10年が経ちました。社会の至る所でほころびが目立ち始めました。パソコンの前に座って株取引をするだけで大儲けする人もいれば、ネットカフェ難民やワーキングプアなどという言葉も生まれました。ここまで生きにくい世の中なのだから、何かにすがりつきたくなるのは当然です。そのうちの一つが小泉首相であり、もうひとつが、江原啓之氏に代表されるスピリチュアル・ブームです。
江原氏の講演会はたいへんな人気だそうです。今ではブームは過ぎたと言われます。たしかに、テレビで見ることは少なくなりました。でも、若い女性たちの間ではまだスピリチュアルは廃れていません。日本国内の「パワースポット」には行列ができているとの話です。つい最近も、若い人気歌手とお笑いタレントが、わざわざアメリカのパワースポットに行っていたとワイドショーで話題になっていました。
江原氏に代わってここ数年人気になっているのが、勝間和代氏です。「カツマー」なんて呼ばれる熱心なファンが多くいることも知られています。確実な論拠はありませんが、江原氏の講演に詰め掛けた人たちが、勝間氏に流れたのではないかと考えています。結局、なにかにすがりたいとの思いは同じでしょう。それゆえ、精神科医の香山リカ氏が「<勝間和代>を目指さない」と警鐘を鳴らした本がベストセラーになり、ちょっとした議論になりました。
私は、10年前、五木先生を凝視していた女性の目を忘れることはできません。おそらく、江原啓之氏の講演では、あの目をした人たちが演壇を熱いまなざしで見つめていたのでしょう。江原氏だけではなく、若い女性向けのセミナーでは、とにかく何かを得ようとか、何かを摑もうというヒリヒリとした痛々しさがあるそうです。それは、時代の大変さと、そのなかで女性が置かれた厳しい立場を物語っています。
幸い、五木先生の講演会では、そのような重い空気はありませんでした。もし江原啓之氏や勝間和代氏らに向けられるような、何者かにすがる空気では、私は耐えられなかったでしょう。それはつまり、すこしは空気が弛緩していたからだとも言えますし、主な客層が中高年から高齢者だったからとも考えられます。
ただ、単純に、よかったよかったでは済まされないでしょう。おそらく別の講演会やセミナーでは、10年前よりもさらに厳しい視線が一斉に演壇に注がれでいたでしょうから。
以上、いただいたコメントへの私からの答えです。
今度はまともな文学議論をしたいものですね。こんな枝葉末節や揚げ足取りではなく。