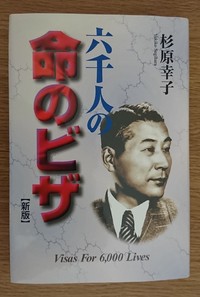2008年01月27日12:25
チャータースクールの今?≫
カテゴリー │書籍・雑誌
まったく期待せずに手に取った本が、実は掘り出し物だったということはしばしばある話です。今回紹介するのもそんな一冊です。ノンフィクションライターの林壮一氏による『アメリカ下層教育現場』(光文社新書)です。
林氏はひょんなことからカジノの街リノのチャーターハイスクールの講師に就任します。生徒は低所得の母子家庭で育ったり、里親に育てられたり、刑務所を出たり入ったりを繰り返す親に育てられ、生徒も時給何ドルで働いている人もいます。学校の場所も麻薬の売人がうようよしており、護身用に銃を持つ生徒もいます。
そこに乗り込んだ元プロボクサーの著者は、クラスの建て直しを試みます。さしずめアメリカ版「スクール・ウォーズ」です。ただひとつ、山下真司と決定的に異なるのは、落ちこぼれ生徒を救うことを投げ出してしまうことです。
著者が講師をした「レインシャドウ・コミュニティー・チャーター・ハイスクール」は、公立高校に通えない生徒が仕方なく通うところです。退学したり授業をサボる生徒も多くいます。日本では「教育困難校」なんて呼ばれているところでしょうか。著者みずから
「私はどんなことをしても、自分の息子をこんな学校にはやりたくないと感じた」
「「シエラ・ビスタ・エレメンタリー・スクール(引用者注・著者が後にボランティアをした公立初等学校)から、レインシャドウ・コミュニティー・チャーター・ハイスクールに進学する子を出してはならないと思っています」」
と書くくらいですから。
私はこの実情に驚きました。
林氏はひょんなことからカジノの街リノのチャーターハイスクールの講師に就任します。生徒は低所得の母子家庭で育ったり、里親に育てられたり、刑務所を出たり入ったりを繰り返す親に育てられ、生徒も時給何ドルで働いている人もいます。学校の場所も麻薬の売人がうようよしており、護身用に銃を持つ生徒もいます。
そこに乗り込んだ元プロボクサーの著者は、クラスの建て直しを試みます。さしずめアメリカ版「スクール・ウォーズ」です。ただひとつ、山下真司と決定的に異なるのは、落ちこぼれ生徒を救うことを投げ出してしまうことです。
著者が講師をした「レインシャドウ・コミュニティー・チャーター・ハイスクール」は、公立高校に通えない生徒が仕方なく通うところです。退学したり授業をサボる生徒も多くいます。日本では「教育困難校」なんて呼ばれているところでしょうか。著者みずから
「私はどんなことをしても、自分の息子をこんな学校にはやりたくないと感じた」
「「シエラ・ビスタ・エレメンタリー・スクール(引用者注・著者が後にボランティアをした公立初等学校)から、レインシャドウ・コミュニティー・チャーター・ハイスクールに進学する子を出してはならないと思っています」」
と書くくらいですから。
私はこの実情に驚きました。
私がフリースクールやホームエデュケーションについて研究していた約8年くらいまえ、公教育以外の教育制度としてひとつのモデルとされていたのが、このチャータースクールです。チャータースクールとは、日本でいう文部科学省や地方自治体以外の役所から委任状(チャーター)を受けて開設されている学校です。正規の学校で、予算も与えられ、卒業したらちゃんと学卒の資格も持てます。教育管轄官庁の方針(日本では学習指導要領)から外れて、自由なカリキュラムが組めます。障害児専門の学校や、環境問題を中心に学ぶ学校などの事例を本で読みました。
その代わり、一定の期間であらかじめ申請した数値目標まで生徒の成績が上がらなければ、容赦なくチャーターは取り上げられ、廃校になります。ここがアメリカの厳しいところです。アメリカの教育の最大の問題は全体の学力の底上げですから、いくら高邁な理想を掲げていようとも、学力がついてこなかったらダメなのです。当然、調査のための学力テストもあり、自分の学校が州や地域で何番かということも明白になります。このあたりは日米教育事情の根本的な違いですから、どっちがいいとは言えません。
この本を読んで、チャータースクールが、私が抱いていた印象と、まるっきり逆の機能を果たしてしまっていると感じました。もちろん、著者の主観的なリポートですから、真に受けることもできませんが。
考えてみれば、アメリカは日本以上の学歴社会で、収入がいい仕事に就くためにはエリート学校から大学に行かなくてはなりません。多様な価値観を取り入れた教育といっても、高収入の家庭ではアイビーリーグなどへ行ける学校に子弟を通わせるのが当然の選択です。このあたりも日本では昔から見られることです。チャータースクールが下層階層の子どもたちの吹き溜まりとなるのも仕方がないのかもしれません。
日本もいじめや不登校などが問題として認識されてから、教育制度の多様化が進みました。小耳に挟んだところでは、そのなかにはチャータースクール同様に、当初の目的と実態とがかけ離れているところもあるようです。
ゆとり教育の是非だの学力低下だのと話題になりますが、数量的調査だけで百家争鳴するのはちょっと違うとも感じます。とはいえ、日本では教育病理の受け皿として機能してきたオルタナティブ教育についても、そろそろ再研究する時期なのかな、なんて思います。
読み物としても、比較的軽く読め、しかし胸に詰まる箇所が多くある良書です。決して甘くもなく、感動もありませんが。
その代わり、一定の期間であらかじめ申請した数値目標まで生徒の成績が上がらなければ、容赦なくチャーターは取り上げられ、廃校になります。ここがアメリカの厳しいところです。アメリカの教育の最大の問題は全体の学力の底上げですから、いくら高邁な理想を掲げていようとも、学力がついてこなかったらダメなのです。当然、調査のための学力テストもあり、自分の学校が州や地域で何番かということも明白になります。このあたりは日米教育事情の根本的な違いですから、どっちがいいとは言えません。
この本を読んで、チャータースクールが、私が抱いていた印象と、まるっきり逆の機能を果たしてしまっていると感じました。もちろん、著者の主観的なリポートですから、真に受けることもできませんが。
考えてみれば、アメリカは日本以上の学歴社会で、収入がいい仕事に就くためにはエリート学校から大学に行かなくてはなりません。多様な価値観を取り入れた教育といっても、高収入の家庭ではアイビーリーグなどへ行ける学校に子弟を通わせるのが当然の選択です。このあたりも日本では昔から見られることです。チャータースクールが下層階層の子どもたちの吹き溜まりとなるのも仕方がないのかもしれません。
日本もいじめや不登校などが問題として認識されてから、教育制度の多様化が進みました。小耳に挟んだところでは、そのなかにはチャータースクール同様に、当初の目的と実態とがかけ離れているところもあるようです。
ゆとり教育の是非だの学力低下だのと話題になりますが、数量的調査だけで百家争鳴するのはちょっと違うとも感じます。とはいえ、日本では教育病理の受け皿として機能してきたオルタナティブ教育についても、そろそろ再研究する時期なのかな、なんて思います。
読み物としても、比較的軽く読め、しかし胸に詰まる箇所が多くある良書です。決して甘くもなく、感動もありませんが。