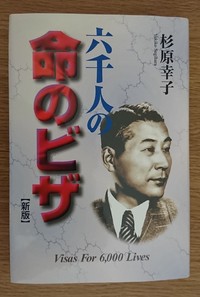2011年09月11日11:22
東日本大震災から半年です≫
カテゴリー │書籍・雑誌
今日は9月11日。東日本大震災から半年です。犠牲になられた方に心からお悔やみを申し上げるとともに、被災された方々と地域の復興をお祈り申し上げます。
今回は、いまだ終息しない原子力発電所についての本を紹介します。
開沼博『「フクシマ」論 原子力ムラはなぜ生まれたのか』(青土社)です。
筆者は福島県いわき市出身、東京大学大学院博士課程に在籍中の若い社会学者です。
吉見俊哉や上野千鶴子に師事し、渾身の修士論文に「3・11」後の論考を加え出版されたのが本作です。
「原子力ムラ」というと、企業・政治家・官僚・学者・報道の持ちつ持たれつの世界(元NHK科学ジャーナリストの小出五郎氏のいう「原子力ファミリー・ペンタゴン」)を揶揄した言葉ですが、ここではその意味ではなく、本来の「ムラ」、すなわち原発が立地している双葉郡について書かれた論文です。
原発と地元民というと、国と電力会社が「アメとムチ」で抑えつける印象があります。「ミツバチの羽音と地球の回転」(鎌仲ひとみ監督)というドキュメンタリー映画を観ましたが、そこでも反対運動をする瀬戸内海の祝島の島民を四国電力や経済産業省が無視して埋め立て計画を実行し、その一方で莫大な補償金を払い込むというシーンがあります。
この本に描かれる「フクシマ」の姿は、そんなある意味「ナイーブ」な二項対立ではありません。そこには、地元住民が原発を主体的に受け入れる、筆者の記述に依ると、「幸福」な関係があります。
今回は、いまだ終息しない原子力発電所についての本を紹介します。
開沼博『「フクシマ」論 原子力ムラはなぜ生まれたのか』(青土社)です。
筆者は福島県いわき市出身、東京大学大学院博士課程に在籍中の若い社会学者です。
吉見俊哉や上野千鶴子に師事し、渾身の修士論文に「3・11」後の論考を加え出版されたのが本作です。
「原子力ムラ」というと、企業・政治家・官僚・学者・報道の持ちつ持たれつの世界(元NHK科学ジャーナリストの小出五郎氏のいう「原子力ファミリー・ペンタゴン」)を揶揄した言葉ですが、ここではその意味ではなく、本来の「ムラ」、すなわち原発が立地している双葉郡について書かれた論文です。
原発と地元民というと、国と電力会社が「アメとムチ」で抑えつける印象があります。「ミツバチの羽音と地球の回転」(鎌仲ひとみ監督)というドキュメンタリー映画を観ましたが、そこでも反対運動をする瀬戸内海の祝島の島民を四国電力や経済産業省が無視して埋め立て計画を実行し、その一方で莫大な補償金を払い込むというシーンがあります。
この本に描かれる「フクシマ」の姿は、そんなある意味「ナイーブ」な二項対立ではありません。そこには、地元住民が原発を主体的に受け入れる、筆者の記述に依ると、「幸福」な関係があります。
原発事故が起こってから、「原子力ムラ」の地元民は自主・強制問わず避難・退去させられました。避難所で寝泊まりする人たちが東京電力や政府に怒りの声を挙げているのをテレビで観ました。東電本店前での抗議デモの報道もありました。ところが同書で筆者が聞き書きした地元民の声は、だいぶ違います。
「東京の人は普段は何にも感心がないのに、なんかあるとすぐ危ない危ないって大騒ぎするんだから。一番落ち着いてるのは地元の私たちですから。ほっといてくださいって思います。(富岡町、五〇代、女性)」
「まあ、内心はないならないほうがいいっていうのはみんな思ってはいるんです。でも「言うのはやすし」で、だれも口はださない。出稼ぎ行って、家族ともはなれて危ないとこ行かされるのなんかよりよっぽどいいんじゃないかっていうのが今の考えですよ。(大熊町、五〇代、女性)」
「3・11」以前のインタビューとはいえ、中央のメディアからの情報とはかなり温度差があります。
筆者はジョン・ダワーの『敗北を抱きしめて』などを参照しながら、「原子力ムラ」が原発を「包摂」し、「自発的かつ自動的に」服従していく(されていく)様子を論じています。
ごく簡単かつ乱暴に言えば、「福島のチベット」(言葉の是非はここでは置いておきます)とも呼ばれ、飢餓の危険もあるほどの貧困地帯だった双葉郡は、戦前戦後とエネルギー供給地帯となりました。戦前は中央から一方的に押し付けられましたが、戦後は民選知事や地元出身国会議員ら「メディエーター(媒介者)」が積極的に誘致していきます。かくして福島第一原発はたいして問題にもされず建設され、工事関係者や電力会社の人たちで町は潤いました。
高度成長期になると原発の負の面も言われるようになりました。そんな中で福島第二原発は苦難の末に建設され、かたや東北電力の浪江・小高原発はいまだ建設に着手されていません。それでも地元は経済的な利益と都会の消費社会がムラにやってくることで、原発を取り込んでいき、逆に取り込まれていきます。
90年代前後から、チェルノブイリやJCOの事故、電力会社のトラブル隠しなどが明るみに出て、一方では財政も逼迫します。佐藤栄佐久知事は、「保守本流ゆえの反原発」の立場で中央と対峙しました。ここでは利害調整のため中央に送りこまれた「メディエーター」は、「コーディネーター」から「ノイズメーカー」に姿を変えます。ところが佐藤栄佐久知事が収賄で逮捕されると(この件も本論では置いておきます)、「メディエーター」なくしても中央と地方(「原子力ムラ」)との共存関係が成り立ち、自発的な服従のシステムが完成しました。
以上、本書の「終章」を主に、私がまとめたものです。修士論文とはいえ社会学者の専門書なので、取っ付きにくいかもしれませんが、これだけ原発のことが新聞やテレビなどで取り上げられているのですから、十分な予備知識があるはずです。お手にとってください。
本書には、専門家ではない私たちにもなじみ深いエピソードがいくつも出てきます。
サッカーの女子日本代表チーム「なでしこジャパン」がワールドカップに優勝してブームになっていますが、主力選手の丸山桂里奈、鮫島彩はかつて東京電力女子サッカー部「マリーゼ」に所属しており、東電も出資しているサッカーのナショナルトレーニングセンター「Jヴィレッジ」で練習をしています。地元学校ではサッカーの観戦やスポーツ専攻クラスがあります。
「原子力最中」や「回転寿司アトム」「ブックスアトム」などの地元の銘菓・店名などと並んで、「原子力」が地元の「アイデンティティペグ」となっており、中央(≒東京)の文化を再現するメディアとなっています。
別の箇所ではテレビ番組の企画として生まれた「DASH村」についても触れられています。本論からやや離れた部分なのであまり触れませんが、興味のある方は読んでみてください。
学術書としてクリティカルに見ると、批判的な点も出てきます。
一番危ういと思ったことは、地元民が原発を望んだのだから今の惨状は仕方がない、文句を言うな、甘えるなという「自己責任」論を噴出させるおそれがあるということです。
これについては丹念に読めばそんなことはないとわかります(例えば中央との「信頼関係」を、ある学者の言葉を引用して「奴隷の知恵」と表現している)。ただ、私のような、原発についてちょっと報道で聞きかじった程度の理解しかない人は「要注意」でしょう。
フィールドワークの数量や偏りも指摘されています。話を聞いた人が数十名、引用された言説が12名分ですので、かなりの少なさですし、サンプル抽出の恣意性も問題があります。むしろ、他の論文や新聞記事などの資料からの引用のほうが目立ちます。フィールドワークの手法も詳述する必要があります。
「当事者」を双葉郡に限定したあまりに、福島県の他の地域、例えば避難を余儀なくされた飯舘村や南相馬市や、県庁所在地の福島市、筆者の出身地のいわき市などが相対的におろそかになっている点も気にかかります。
そういった学術的な批判は、今後の筆者の研究に役立ててもらいたいと思います。
以前も書きましたが、「3.11」以後に感じたのは、つくづくこの国は「空気」が支配しているということです。
震災発生直後は「がんばろう日本」の大合唱で、続いては過度の自粛ムード、原発の被害が明らかになってくると「東電けしからん」以外は言えない雰囲気になります。その東電サッカー部出身の選手がいるなでしこジャパンが優勝すると「おめでとうなでしこ」「感動をありがとう」となります。
もちろん、いうべき点はどんどん主張するべきです。でも、少数意見を封殺したりフルボッコにしたりするのはファシズムと代わりません。
私個人の意見ですが、「脱原発」の主張には全面的な賛同はできません。反対でもありませんが、留保の態度を取っています。でも、これを表明することすら、今の風潮では勇気が必要です。
著者が言うように、安易な二項対立からは見えなくなってしまいます。それを見ようとする本書の意義は大きいものです。それと同じように、震災だけでなく、戦争や9・11のアメリカように、一方の意見だけに流されやすい非常時や、イデオロギーの対立に陥りやすい原発問題で、冷静に「ちょっと待て!」と思考を立ち止まらせ、「第三の道」を模索することも必要なことです。
「東京の人は普段は何にも感心がないのに、なんかあるとすぐ危ない危ないって大騒ぎするんだから。一番落ち着いてるのは地元の私たちですから。ほっといてくださいって思います。(富岡町、五〇代、女性)」
「まあ、内心はないならないほうがいいっていうのはみんな思ってはいるんです。でも「言うのはやすし」で、だれも口はださない。出稼ぎ行って、家族ともはなれて危ないとこ行かされるのなんかよりよっぽどいいんじゃないかっていうのが今の考えですよ。(大熊町、五〇代、女性)」
「3・11」以前のインタビューとはいえ、中央のメディアからの情報とはかなり温度差があります。
筆者はジョン・ダワーの『敗北を抱きしめて』などを参照しながら、「原子力ムラ」が原発を「包摂」し、「自発的かつ自動的に」服従していく(されていく)様子を論じています。
ごく簡単かつ乱暴に言えば、「福島のチベット」(言葉の是非はここでは置いておきます)とも呼ばれ、飢餓の危険もあるほどの貧困地帯だった双葉郡は、戦前戦後とエネルギー供給地帯となりました。戦前は中央から一方的に押し付けられましたが、戦後は民選知事や地元出身国会議員ら「メディエーター(媒介者)」が積極的に誘致していきます。かくして福島第一原発はたいして問題にもされず建設され、工事関係者や電力会社の人たちで町は潤いました。
高度成長期になると原発の負の面も言われるようになりました。そんな中で福島第二原発は苦難の末に建設され、かたや東北電力の浪江・小高原発はいまだ建設に着手されていません。それでも地元は経済的な利益と都会の消費社会がムラにやってくることで、原発を取り込んでいき、逆に取り込まれていきます。
90年代前後から、チェルノブイリやJCOの事故、電力会社のトラブル隠しなどが明るみに出て、一方では財政も逼迫します。佐藤栄佐久知事は、「保守本流ゆえの反原発」の立場で中央と対峙しました。ここでは利害調整のため中央に送りこまれた「メディエーター」は、「コーディネーター」から「ノイズメーカー」に姿を変えます。ところが佐藤栄佐久知事が収賄で逮捕されると(この件も本論では置いておきます)、「メディエーター」なくしても中央と地方(「原子力ムラ」)との共存関係が成り立ち、自発的な服従のシステムが完成しました。
以上、本書の「終章」を主に、私がまとめたものです。修士論文とはいえ社会学者の専門書なので、取っ付きにくいかもしれませんが、これだけ原発のことが新聞やテレビなどで取り上げられているのですから、十分な予備知識があるはずです。お手にとってください。
本書には、専門家ではない私たちにもなじみ深いエピソードがいくつも出てきます。
サッカーの女子日本代表チーム「なでしこジャパン」がワールドカップに優勝してブームになっていますが、主力選手の丸山桂里奈、鮫島彩はかつて東京電力女子サッカー部「マリーゼ」に所属しており、東電も出資しているサッカーのナショナルトレーニングセンター「Jヴィレッジ」で練習をしています。地元学校ではサッカーの観戦やスポーツ専攻クラスがあります。
「原子力最中」や「回転寿司アトム」「ブックスアトム」などの地元の銘菓・店名などと並んで、「原子力」が地元の「アイデンティティペグ」となっており、中央(≒東京)の文化を再現するメディアとなっています。
別の箇所ではテレビ番組の企画として生まれた「DASH村」についても触れられています。本論からやや離れた部分なのであまり触れませんが、興味のある方は読んでみてください。
学術書としてクリティカルに見ると、批判的な点も出てきます。
一番危ういと思ったことは、地元民が原発を望んだのだから今の惨状は仕方がない、文句を言うな、甘えるなという「自己責任」論を噴出させるおそれがあるということです。
これについては丹念に読めばそんなことはないとわかります(例えば中央との「信頼関係」を、ある学者の言葉を引用して「奴隷の知恵」と表現している)。ただ、私のような、原発についてちょっと報道で聞きかじった程度の理解しかない人は「要注意」でしょう。
フィールドワークの数量や偏りも指摘されています。話を聞いた人が数十名、引用された言説が12名分ですので、かなりの少なさですし、サンプル抽出の恣意性も問題があります。むしろ、他の論文や新聞記事などの資料からの引用のほうが目立ちます。フィールドワークの手法も詳述する必要があります。
「当事者」を双葉郡に限定したあまりに、福島県の他の地域、例えば避難を余儀なくされた飯舘村や南相馬市や、県庁所在地の福島市、筆者の出身地のいわき市などが相対的におろそかになっている点も気にかかります。
そういった学術的な批判は、今後の筆者の研究に役立ててもらいたいと思います。
以前も書きましたが、「3.11」以後に感じたのは、つくづくこの国は「空気」が支配しているということです。
震災発生直後は「がんばろう日本」の大合唱で、続いては過度の自粛ムード、原発の被害が明らかになってくると「東電けしからん」以外は言えない雰囲気になります。その東電サッカー部出身の選手がいるなでしこジャパンが優勝すると「おめでとうなでしこ」「感動をありがとう」となります。
もちろん、いうべき点はどんどん主張するべきです。でも、少数意見を封殺したりフルボッコにしたりするのはファシズムと代わりません。
私個人の意見ですが、「脱原発」の主張には全面的な賛同はできません。反対でもありませんが、留保の態度を取っています。でも、これを表明することすら、今の風潮では勇気が必要です。
著者が言うように、安易な二項対立からは見えなくなってしまいます。それを見ようとする本書の意義は大きいものです。それと同じように、震災だけでなく、戦争や9・11のアメリカように、一方の意見だけに流されやすい非常時や、イデオロギーの対立に陥りやすい原発問題で、冷静に「ちょっと待て!」と思考を立ち止まらせ、「第三の道」を模索することも必要なことです。