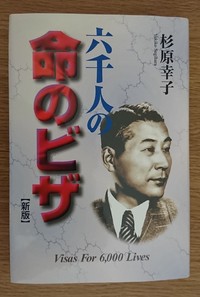2010年02月21日04:58
一週間のご無沙汰でした≫
カテゴリー │書籍・雑誌
用事に追われて気ぜわしく一週間が過ぎ、更新もサボってしまいました。その間に玉置宏さんが亡くなり、「あー、内職仕事する母の横でラジオの『笑顔でこんにちは』聞いてたなー」と感慨にふけり、そしたら藤田まことが亡くなり、「あー、オガノリ(小川範子)のお父さんもかー。時代劇もよかったけど、『はぐれ刑事』の素朴な役柄もよかったな」なんてさらなる感慨にふけってしまいました。またオリンピックでも日本勢ががんばっています。ついつい五輪中継に見入ってしまうのが多忙の原因でしょうね。
そんななかで読了した本をひとつ。すでにベストセラーになっている堤未果『ルポ貧困大国アメリカⅡ』(岩波新書)。前著『貧困大国アメリカ』(同)が大好評を博した著者の、オバマ政権後のアメリカをリポートした新著です。
前著はブッシュ政権の「落ちこぼれゼロ法」が予算配分をめぐる学校間の競争をあおり、学費や医療費が支払えない低所得者層が巨大産業となった軍に入隊して戦場に送られるという衝撃的な内容でした。私以外にもショックだった人は多いようで、権威ある賞を受賞しています。
その後、「年越し派遣村」の湯浅誠氏との共著『正社員が没落する』(角川Oneテーマ新書)で、極端な民営化が貧困層だけではなく中流層のホワイトカラーの生活まで蝕んでいる様子をリポートしています。同書で彼女がテーマにしたのは、サラリーマンでなく、高給取りであるはずの医師がフードスタンプ(貧困者やホームレスを対象にした食糧配給チケット)を受給するまでに落ちぶれる様子でした。
今回の『Ⅱ』も、力作のルポとなっています。ただ、前著などと比較して、読みながら私の頭に引っかかっていた違和感が少しずつ膨らんでいきました。
「これって本当に、アメリカのルポ?日本の話じゃないの?」
そんななかで読了した本をひとつ。すでにベストセラーになっている堤未果『ルポ貧困大国アメリカⅡ』(岩波新書)。前著『貧困大国アメリカ』(同)が大好評を博した著者の、オバマ政権後のアメリカをリポートした新著です。
前著はブッシュ政権の「落ちこぼれゼロ法」が予算配分をめぐる学校間の競争をあおり、学費や医療費が支払えない低所得者層が巨大産業となった軍に入隊して戦場に送られるという衝撃的な内容でした。私以外にもショックだった人は多いようで、権威ある賞を受賞しています。
その後、「年越し派遣村」の湯浅誠氏との共著『正社員が没落する』(角川Oneテーマ新書)で、極端な民営化が貧困層だけではなく中流層のホワイトカラーの生活まで蝕んでいる様子をリポートしています。同書で彼女がテーマにしたのは、サラリーマンでなく、高給取りであるはずの医師がフードスタンプ(貧困者やホームレスを対象にした食糧配給チケット)を受給するまでに落ちぶれる様子でした。
今回の『Ⅱ』も、力作のルポとなっています。ただ、前著などと比較して、読みながら私の頭に引っかかっていた違和感が少しずつ膨らんでいきました。
「これって本当に、アメリカのルポ?日本の話じゃないの?」
異様なまでに既視感を感じるのです。例えば、冒頭に大学の学費値上げと奨学金の話が出てきます。アメリカは奨学金制度が充実しているとされていました。「私がクマにキレた理由」という映画では、ハーバードに入学する学生が手にいっぱいのパンフレットを見ながら「奨学制度っていっぱいあるのね」と悩むシーンがあります。
でも、それは誤解で、一部のエリート校、アイビー・プラスと呼ばれる名門大学だけの話だそうです(ハーバードももちろんそう)。卒業生は成功者として金持ちになり、のちに巨額の寄付金が約束されるからです。そうではない大学は、補助金が減らされ、学費が値上げされます(エリート校とそれ以外の格差の理解についてはこちらの記事が役に立ちます)。
アメリカは自由の国どころか日本以上の学歴主義で、大学に行かなければファストフードの従業員など非正規雇用しかありません。ですから中流層は、給付型奨学金だけでなく、高利の学資ローンを契約して大学に進みます。そのローンがいつの間にか膨れ上がり、多額の借金を抱え込み、返済に追われ、破産します。破産したらクレジットカードは作れず、アメリカはカード社会なので、生活に行き詰ります。
これと似た話を、最近日本のネットで目にしました。いわゆる「高学歴ワーキングプア」の話です(「“高学歴ワーキングプア”が急増中! 「官製資格ビジネス」に乗せられた博士たちの悲痛」)。
記事そのものに新鮮味はありません。大学関係者ならばよくご存じの話です。就職するために、あるいは研究のために大学や大学院に進学したのはいいが、卒業・修了後の受け皿がない。日本の奨学金の多くは給付型ではなく「貸与型」で、筆者が言うように、学資ローンと呼んだほうがいいものです。学部4年間、院までならば博士課程までで計9年間の奨学金は、利息まで含めるといくらになるでしょう。しかも、返済できるあてはありません。
このように、日本の現状や近未来の姿とパラレルな描写が、堤氏の著書には多数出てきます。
他にも、高齢者の年金破たん。GMが提供するはずだった年金をあてにした退職後の生活が狂い、年老いても量販店やウォルマートで働かなくてはいけない事情が描かれます。
それから、高額医療費と、政治と保険業界(「医産複合体」)の癒着構造。政治家に巨額の政治資金提供をしている医療業界によって、「単一支払い皆保険制度」法案が骨抜きにされたことは日本の新聞でも報じられました。保険証を持たない人が、受け入れ拒否できないERや医療費が比較的安いプライマリケア医師(日本で言う開業医)に殺到し、現場の医療関係者が疲れ果て、ERを閉鎖する病院やプライマリケア医師の廃業が続出し、医療過疎となっています。
いずれも、日本と大同小異です。
極度の市場原理主義のツケで、貧困層やマイノリティだけでなく、つつましやかに働いてきた中間層までが十分な公的サービスを受けられないことは、マイケル・ムーア監督の映画でおなじみの光景です。本書でもムーア監督の「シッコ」「キャピタリズム」などと同様の描写が多く出てきています。
日本と異なり、しかしショッキングだったのが、刑務所の民営化です。刑務所を「投資」(投機?)として商品化する金融マンにより、受刑者を安い労働力として企業に売りつけます。黙々と作業を行い、ストを起こす心配もなく、社会保障の負担もなく、しかも第三世界の労働者よりもはるかに安くこき使える囚人は企業にとって魅力的です。
本に書かれていた受刑者の労働として、危険な重労働のほかに、電話交換手があります。今では人件費削減のために、中国やインドにオペレーションセンターを置いている企業は少なくありません。しかしそれだと担当部署をたらいまわしにされた揚句、オペレーターが言葉が不自由で専門的な意思疎通ができないなど苦情があるそうです。受刑者を使えば、そんな心配もありません。もちろん、人件費はかなり安くなります。
需要が多いため、刑務所には囚人が詰め込まれ、さらに、ホームレスを犯罪者として取り締まりを強化する動きがあります。
いくらなんでも日本ではここまではないだろう、と思いましたが、日本でもPFI(民間資本導入)方式の刑務所もあり、アメリカとはかなり違うようですが、大丈夫かなと不安になりました。
今回もかなりの力作で、ベストセラーになるのも無理はないと思いました。ただ、水を差すと、逆の意見もまた聞いてみたいと思いました。
ルポルタージュとしては、まるで、自分の主張に沿う証言だけを一方的に追って行ったような取材のようにも感じられました。
意外なことに、というか実は以外ではないのですが、筆者はオバマ政権の政策を支持していません。これは、オバマ大統領がアフガンへの増兵を進めたり、医療保険改革で大幅な譲歩をしたりと、リベラルから中道へと軸足を移しつつあることがあります。
それに対して異を唱えることは決して悪くありません。でも、ルポルタージュの手法として、都合のいい事実だけを集めることは適切ではありません。本人にそのつもりがなくとも、疑いを持たれるだけで、つまらない異論を持つ人に付け入るすきを与えてしまいます。ちゃんとした反論ではなく、サヨク嫌いのヘタレ保守陣営による揚げ足取りのような。
前作に比べて遜色のない本ですが、ちょっとそのところが気になったかな、という思いがしました。
長く書きすぎてしまいましたが、おすすめの本です。ルポなので平明に書かれていますし、新書ですから700円ちょっとで買えます。
内容が内容だけにスラスラと気分よく読むということはできませんが、忙しい方にも、いや、多忙な方にこそ読んでもらいたい本です。
でも、それは誤解で、一部のエリート校、アイビー・プラスと呼ばれる名門大学だけの話だそうです(ハーバードももちろんそう)。卒業生は成功者として金持ちになり、のちに巨額の寄付金が約束されるからです。そうではない大学は、補助金が減らされ、学費が値上げされます(エリート校とそれ以外の格差の理解についてはこちらの記事が役に立ちます)。
アメリカは自由の国どころか日本以上の学歴主義で、大学に行かなければファストフードの従業員など非正規雇用しかありません。ですから中流層は、給付型奨学金だけでなく、高利の学資ローンを契約して大学に進みます。そのローンがいつの間にか膨れ上がり、多額の借金を抱え込み、返済に追われ、破産します。破産したらクレジットカードは作れず、アメリカはカード社会なので、生活に行き詰ります。
これと似た話を、最近日本のネットで目にしました。いわゆる「高学歴ワーキングプア」の話です(「“高学歴ワーキングプア”が急増中! 「官製資格ビジネス」に乗せられた博士たちの悲痛」)。
記事そのものに新鮮味はありません。大学関係者ならばよくご存じの話です。就職するために、あるいは研究のために大学や大学院に進学したのはいいが、卒業・修了後の受け皿がない。日本の奨学金の多くは給付型ではなく「貸与型」で、筆者が言うように、学資ローンと呼んだほうがいいものです。学部4年間、院までならば博士課程までで計9年間の奨学金は、利息まで含めるといくらになるでしょう。しかも、返済できるあてはありません。
このように、日本の現状や近未来の姿とパラレルな描写が、堤氏の著書には多数出てきます。
他にも、高齢者の年金破たん。GMが提供するはずだった年金をあてにした退職後の生活が狂い、年老いても量販店やウォルマートで働かなくてはいけない事情が描かれます。
それから、高額医療費と、政治と保険業界(「医産複合体」)の癒着構造。政治家に巨額の政治資金提供をしている医療業界によって、「単一支払い皆保険制度」法案が骨抜きにされたことは日本の新聞でも報じられました。保険証を持たない人が、受け入れ拒否できないERや医療費が比較的安いプライマリケア医師(日本で言う開業医)に殺到し、現場の医療関係者が疲れ果て、ERを閉鎖する病院やプライマリケア医師の廃業が続出し、医療過疎となっています。
いずれも、日本と大同小異です。
極度の市場原理主義のツケで、貧困層やマイノリティだけでなく、つつましやかに働いてきた中間層までが十分な公的サービスを受けられないことは、マイケル・ムーア監督の映画でおなじみの光景です。本書でもムーア監督の「シッコ」「キャピタリズム」などと同様の描写が多く出てきています。
日本と異なり、しかしショッキングだったのが、刑務所の民営化です。刑務所を「投資」(投機?)として商品化する金融マンにより、受刑者を安い労働力として企業に売りつけます。黙々と作業を行い、ストを起こす心配もなく、社会保障の負担もなく、しかも第三世界の労働者よりもはるかに安くこき使える囚人は企業にとって魅力的です。
本に書かれていた受刑者の労働として、危険な重労働のほかに、電話交換手があります。今では人件費削減のために、中国やインドにオペレーションセンターを置いている企業は少なくありません。しかしそれだと担当部署をたらいまわしにされた揚句、オペレーターが言葉が不自由で専門的な意思疎通ができないなど苦情があるそうです。受刑者を使えば、そんな心配もありません。もちろん、人件費はかなり安くなります。
需要が多いため、刑務所には囚人が詰め込まれ、さらに、ホームレスを犯罪者として取り締まりを強化する動きがあります。
いくらなんでも日本ではここまではないだろう、と思いましたが、日本でもPFI(民間資本導入)方式の刑務所もあり、アメリカとはかなり違うようですが、大丈夫かなと不安になりました。
今回もかなりの力作で、ベストセラーになるのも無理はないと思いました。ただ、水を差すと、逆の意見もまた聞いてみたいと思いました。
ルポルタージュとしては、まるで、自分の主張に沿う証言だけを一方的に追って行ったような取材のようにも感じられました。
意外なことに、というか実は以外ではないのですが、筆者はオバマ政権の政策を支持していません。これは、オバマ大統領がアフガンへの増兵を進めたり、医療保険改革で大幅な譲歩をしたりと、リベラルから中道へと軸足を移しつつあることがあります。
それに対して異を唱えることは決して悪くありません。でも、ルポルタージュの手法として、都合のいい事実だけを集めることは適切ではありません。本人にそのつもりがなくとも、疑いを持たれるだけで、つまらない異論を持つ人に付け入るすきを与えてしまいます。ちゃんとした反論ではなく、サヨク嫌いのヘタレ保守陣営による揚げ足取りのような。
前作に比べて遜色のない本ですが、ちょっとそのところが気になったかな、という思いがしました。
長く書きすぎてしまいましたが、おすすめの本です。ルポなので平明に書かれていますし、新書ですから700円ちょっとで買えます。
内容が内容だけにスラスラと気分よく読むということはできませんが、忙しい方にも、いや、多忙な方にこそ読んでもらいたい本です。
この記事へのコメント
非正規雇用・有期雇用を禁止せず、抜け穴派遣法改正を強行するなら、
民主党の単独過半数に反対です。次期選挙は、自公だけでなく、
民主党にも投票しません。
関連する重要情報です。
派遣法抜本改正に待ったをかけるJSGU - 明日へのうた - Yahoo!ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/shosuke765/31768018.html
2010/2/20(土) 午前 11:07
この17日、厚生労働省が労働政策諮問委員会に労働者派遣法の改正案要綱を諮
問した。18日に共産党志位委員長は記者会見で「製造業の常用派遣を禁止の例外
としていること、登録型派遣に専門26業種を認めている。この二つの『大穴』は
許されない」と抜本改正への運動強化を呼びかけた。
民主党連立政権下でつくられようとしているこの改正案に多大な影響力を持って
いるのが、連合・UIゼンセン傘下で派遣会社と派遣労働者によって組織されてい
る労働組合「人材サービスゼネラルユニオン(JSGU・07年9月現在42,5
62人)」である。JSGUは最近「労働者派遣制度に関するJSGUの考え方」
なる文書を発表して、派遣法抜本改正論議に待ったをかけている。JSGUのホー
ムページによれば彼ら主張の根拠はおおよそ次のようなものと見られる。
「(派遣法施行以来)派遣事業所は41,966となり、派遣労働者数も321
万人、年間売上高は5兆4,189億円と大きく成長しています」「派遣イコール
『ワーキングプア』、派遣イコール『不本意な働き方』という見方には強く違和感
を覚えます」「職業選択の自由の下、間接雇用も直接雇用も同等に『労働』である
ことの評価がされるべきです」・・・・
実際に派遣で働いている労働者の声として「やりたい仕事を、働きたい時間に、
働きたい期間、働きたい場所で働ける」「時間を有効に活用できる」「多数の派遣
先の中からやりたい仕事を選べる」「仕事より生活を重視し、働き方・暮らし方を
自ら選べる柔軟な制度」など派遣制度を肯定していると主張。「登録型派遣は今や
不可欠な制度として機能している」と結論づけている。
またJSIUは、民主党内に「派遣制度の改善を推進する議員連盟」を立ち上げ
て、「一部団体・政党が主張している『労働者派遣制度の問題の捉え方』の誤りを
指摘し、真の労働者保護と業界の健全な発展を目指して活動」している。議員連盟
の会長は川端達夫衆議院議員、幹事長は三井辨雄議員、他に松原仁、池口修次、加
藤公一、近藤洋介、徳永久志、鷲尾英一郎氏らが役員に名を連ねている。
UIゼンセンは連合の最大民間単産であり、JSGUはその中の有力単産である。
連合と民主党の癒着がこでも問題になっているとおれは思う。
Yahoo!ブログ - 明日へのうた
http://blogs.yahoo.co.jp/shosuke765
民主党の単独過半数に反対です。次期選挙は、自公だけでなく、
民主党にも投票しません。
関連する重要情報です。
派遣法抜本改正に待ったをかけるJSGU - 明日へのうた - Yahoo!ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/shosuke765/31768018.html
2010/2/20(土) 午前 11:07
この17日、厚生労働省が労働政策諮問委員会に労働者派遣法の改正案要綱を諮
問した。18日に共産党志位委員長は記者会見で「製造業の常用派遣を禁止の例外
としていること、登録型派遣に専門26業種を認めている。この二つの『大穴』は
許されない」と抜本改正への運動強化を呼びかけた。
民主党連立政権下でつくられようとしているこの改正案に多大な影響力を持って
いるのが、連合・UIゼンセン傘下で派遣会社と派遣労働者によって組織されてい
る労働組合「人材サービスゼネラルユニオン(JSGU・07年9月現在42,5
62人)」である。JSGUは最近「労働者派遣制度に関するJSGUの考え方」
なる文書を発表して、派遣法抜本改正論議に待ったをかけている。JSGUのホー
ムページによれば彼ら主張の根拠はおおよそ次のようなものと見られる。
「(派遣法施行以来)派遣事業所は41,966となり、派遣労働者数も321
万人、年間売上高は5兆4,189億円と大きく成長しています」「派遣イコール
『ワーキングプア』、派遣イコール『不本意な働き方』という見方には強く違和感
を覚えます」「職業選択の自由の下、間接雇用も直接雇用も同等に『労働』である
ことの評価がされるべきです」・・・・
実際に派遣で働いている労働者の声として「やりたい仕事を、働きたい時間に、
働きたい期間、働きたい場所で働ける」「時間を有効に活用できる」「多数の派遣
先の中からやりたい仕事を選べる」「仕事より生活を重視し、働き方・暮らし方を
自ら選べる柔軟な制度」など派遣制度を肯定していると主張。「登録型派遣は今や
不可欠な制度として機能している」と結論づけている。
またJSIUは、民主党内に「派遣制度の改善を推進する議員連盟」を立ち上げ
て、「一部団体・政党が主張している『労働者派遣制度の問題の捉え方』の誤りを
指摘し、真の労働者保護と業界の健全な発展を目指して活動」している。議員連盟
の会長は川端達夫衆議院議員、幹事長は三井辨雄議員、他に松原仁、池口修次、加
藤公一、近藤洋介、徳永久志、鷲尾英一郎氏らが役員に名を連ねている。
UIゼンセンは連合の最大民間単産であり、JSGUはその中の有力単産である。
連合と民主党の癒着がこでも問題になっているとおれは思う。
Yahoo!ブログ - 明日へのうた
http://blogs.yahoo.co.jp/shosuke765
Posted by greenshield at 2010年03月06日 09:49
非正規雇用を放置する労組と民主党の癒着も問題だがマルチポストはもっと嫌われますよ。
Posted by 大橋輝久 at 2010年03月07日 06:48
at 2010年03月07日 06:48
 at 2010年03月07日 06:48
at 2010年03月07日 06:48