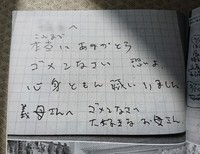2009年04月12日09:55
さあ選挙だ!(ときには真面目に)≫
カテゴリー │政治
♪春はお別れの季節です~、とか♪ミニミニ、見に来てね~、などという歌をついつい口ずさんでしまうと、ああ、私も年食ったなーと妙な感慨にふけってしまいます。なんだかんだ言って、この季節はいいですね。花粉さえなければもっといいんですけどね。
春は出会いと別れの季節といいますが、もうひとつ、今年は選挙の季節でもあります。日本のあちこちでサル山のボス争いが行われ、当地でも今日からドンパチが始まります。拡声器を付けた選挙カーが市内を走り回ります。その脇を自転車でスルスルーっと通り抜けながら、私は思うのです。
「この選挙カーに乗っている人たちは、果たして自転車なんか使うのだろうか。路線バスにも乗るのだろうか」
春は出会いと別れの季節といいますが、もうひとつ、今年は選挙の季節でもあります。日本のあちこちでサル山のボス争いが行われ、当地でも今日からドンパチが始まります。拡声器を付けた選挙カーが市内を走り回ります。その脇を自転車でスルスルーっと通り抜けながら、私は思うのです。
「この選挙カーに乗っている人たちは、果たして自転車なんか使うのだろうか。路線バスにも乗るのだろうか」
身内が倒れてから3か月間、搬送された病院に見舞いに通いました。病院の医師や看護士、その他多くの職員の方々の献身的な努力で、奇跡的に一命を取り止め、近所の病院に転院できるまでになりました。
多くの親戚や友人・知人にもお見舞いに来ていただきました。病院が山の中の茶畑の中にあるため、送り迎えもしてもらいました。「おまえも車乗りーな」「車乗ったほうがいいにー」と勧めてくれる人もたくさんいました。
「いやあ、車怖いんですよ~」と苦笑いをしていましたが、心の中では別のことを思っていました。
「車に『乗らない』のではなく、『乗れない』人もいるってことを知ってくれよ・・・」
私はごく軽い持病を抱えています。普通の人以上に元気なので、とてもそうは見えませんが、それでも薬が手放せません。ハンドルを握ることができるかどうか主治医に聞くと、「自己責任で乗ってください」との言葉が返ってきました。自己責任!これ以上怖い言葉はありません。結果、私は自転車か路線バスで病院まで行くのです。
私のスポーツタイプの自転車で、片道約50分です。冬場に一度チャレンジして「もう絶対やだ!」と泣きながらペダルを漕いだことがありますが、今の季節は最適です。桜吹雪のなかを駆け抜け、新茶の香りを嗅ぎながらのポタリング(軽いサイクリングをこう呼びます)は静岡の自転車乗りだけの特権です。休日はそれでもいいのですが、仕事終わりや緊急時はそうはいきません。30分に一本しか来ないバスに乗って、病院に向かいます。
それでも私はいいのです。母は3か月間、一日も休まず看病に行きました。親戚や友人が車に乗せてくれるときはいいのですが、そうたびたび頼ることはできません。多くは乗り継ぎの待ち時間を含めて片道1時間かけて病院に通っていました。
また、買い物や自分の病院通いは、自転車を使います。私のようなスポーツタイプでなく、婦人用軽快車、いわゆるママチャリです。小雨が降るときも、からっ風が厳しいときも、自転車でスーパーに行っています。私が通販やネットショッピングの利用をすすめても、ケータイすら持たず保守的生活スタイルを変えない六十半ばの母には馬耳東風で、今日も広い駐車場があるヤオハンまでママチャリで走ります。
遠方よりサッカー観戦に来られた方はわかると思いますが、磐田駅の階段を下りてジュビロスタジアム行きのバスの停留所まで行くと、後ろに遠鉄バスの待合所があります。試合があるときには人でいっぱいになりますが、平日の昼間は、腰の曲がったおばあさんや、杖をついたおじいさんや、足をひきずった中年の人がバスを待っています。ときどき制服を着た学生の姿も見えます。
ここにいる人たちは、まぎれもない「交通弱者」です。そして、大多数の市民からは不可視の存在です。
「社会的弱者」という言葉は大嫌いです。「社会的弱者のために」と平気で口にできる人たちはもっと嫌いです。「弱者」といえる人は、相対的に自分が「強者」となります。そして「弱者のために」という言葉は、持てる者が持たざる者に施しを与えているような印象があります。「弱者」という言葉を使う人の多くは、そのことを自覚していません。「パンがなければケーキを食べればいいでしょ」のマリー・アントワネットの有名なフレーズを連想します。
でも、大都市圏に暮らす人以外にとって、自家用車を運転できない人は、間違いなく「弱者」です。障害者、お年寄り、病人、けが人、子ども、低所得者……。彼ら彼女らは(そして私も)、「交通弱者」です。
購買行動も、ロードサイドにある量販店しかない状況だと非常に困ります。電化製品や安い衣類などは通販でもなんとかなりますが、我が家でいちばん困ったのが、ストーブの灯油でした。20リットルのポリタンクを自転車の荷台にくくり付けるのは不可能ですし、何より危険です。
雇用も変わってきます。今度オープンする大規模なショッピングセンターの従業員募集の広告が新聞によく出ています。そこには、大きな駐車場があって、自動車通勤もできることが書かれています。逆に言えば、車がなければ働けません。運転できない人にとっては、雇用機会すら狭められます。
「交通弱者」は「経済的弱者」や「文化的弱者」と重なります。そして「社会的弱者」に連なります。
これは当地だけでなく、日本中で見られる光景です。昨年、仕事の関係で隣の浜松の市長にお会いしましたが、同席していた女性が、「くるくるバス(浜松のコミュニティバス「くるる」のこと)をもっと増やしてください」と、悲痛な声で懇願していました。
同様のバスは当地にもあります。一時間に一本、それも一方通行という不便極まりないものです。口の悪い知人は「年寄りしか乗ってないユーバス(当地のコミュニティバスの愛称)」なんて言っていましたが、それでも病院通いをするようになり、私も時折利用するようになり、お年寄りにとっては数少ない貴重な足なのだと痛感しました。
しかし、問題の本質はそこにはありません。
どうして車がなくては何もできない社会になってしまったのかは、新自由主義社会の推し進めた規制緩和に原因があります。小泉―竹中路線がその流れに棹を差しました。当時の小泉首相は、「痛みをともなう改革」の言葉で国民に我慢を強いました。それはそれで評価できるところもあります。
最大の問題は、真っ先にひどい「痛み」を感じる人が、声を上げることもできない「弱者」だったことです。
交通・都市の問題を論じてきましたが、今日の日本社会のどの分野にでも当てはまることです。私に直近のことだと、医療、福祉、介護、教育、雇用、労働、社会保障、地域社会の崩壊、などなど。副次的効果や潜在的逆機能はもっと多くあります。
この大きすぎる問題に私個人ができることはほとんどありません。せめて、職場や家庭など現場で少しでも改善させていくことしかできません。
ですから、ひとりひとりの有権者が、意欲と能力を持った代表者を責任を持って選び、送り出すことが重要だと思っています。
当地の選挙に立候補した候補者のうち、ブログを持っている方に、今回の文章をトラックバックで送ってみようと思っています。
送られたほうは迷惑でしょうし、そんなことやっても何も変わらないという人もいるでしょうが、何もやらずに不平不満を言うよりは幾分マシだとも思います。
それに、候補者の方々も、そして、今、このブログを見ているあなただって、まるっきり人ごとではないのですから。だって、誰もが年を取るのですから。年を取るってことは、障害者になるってことですから。あるいは不慮の事故や病気や災害で身体の機能を損傷することだって、誰にだって可能性はあるのですから。
そのときになって「車がないと何もできない社会にしやがって」と憤っても遅いですからね。
磐田市長・市議会議員選挙の投票日は4月19日(日曜日)です。
(追記・4月14日)
候補者の方でブログどころかHP持っている人が圧倒的に少なかったorz。
TB受け取った方、トラックバックスパムのように思われるかもしれませんが、そのときには遠慮なく削除してください。
送れなかった候補者の方、無視したわけではありませんのでどうかご容赦ください。
多くの親戚や友人・知人にもお見舞いに来ていただきました。病院が山の中の茶畑の中にあるため、送り迎えもしてもらいました。「おまえも車乗りーな」「車乗ったほうがいいにー」と勧めてくれる人もたくさんいました。
「いやあ、車怖いんですよ~」と苦笑いをしていましたが、心の中では別のことを思っていました。
「車に『乗らない』のではなく、『乗れない』人もいるってことを知ってくれよ・・・」
私はごく軽い持病を抱えています。普通の人以上に元気なので、とてもそうは見えませんが、それでも薬が手放せません。ハンドルを握ることができるかどうか主治医に聞くと、「自己責任で乗ってください」との言葉が返ってきました。自己責任!これ以上怖い言葉はありません。結果、私は自転車か路線バスで病院まで行くのです。
私のスポーツタイプの自転車で、片道約50分です。冬場に一度チャレンジして「もう絶対やだ!」と泣きながらペダルを漕いだことがありますが、今の季節は最適です。桜吹雪のなかを駆け抜け、新茶の香りを嗅ぎながらのポタリング(軽いサイクリングをこう呼びます)は静岡の自転車乗りだけの特権です。休日はそれでもいいのですが、仕事終わりや緊急時はそうはいきません。30分に一本しか来ないバスに乗って、病院に向かいます。
それでも私はいいのです。母は3か月間、一日も休まず看病に行きました。親戚や友人が車に乗せてくれるときはいいのですが、そうたびたび頼ることはできません。多くは乗り継ぎの待ち時間を含めて片道1時間かけて病院に通っていました。
また、買い物や自分の病院通いは、自転車を使います。私のようなスポーツタイプでなく、婦人用軽快車、いわゆるママチャリです。小雨が降るときも、からっ風が厳しいときも、自転車でスーパーに行っています。私が通販やネットショッピングの利用をすすめても、ケータイすら持たず保守的生活スタイルを変えない六十半ばの母には馬耳東風で、今日も広い駐車場があるヤオハンまでママチャリで走ります。
遠方よりサッカー観戦に来られた方はわかると思いますが、磐田駅の階段を下りてジュビロスタジアム行きのバスの停留所まで行くと、後ろに遠鉄バスの待合所があります。試合があるときには人でいっぱいになりますが、平日の昼間は、腰の曲がったおばあさんや、杖をついたおじいさんや、足をひきずった中年の人がバスを待っています。ときどき制服を着た学生の姿も見えます。
ここにいる人たちは、まぎれもない「交通弱者」です。そして、大多数の市民からは不可視の存在です。
「社会的弱者」という言葉は大嫌いです。「社会的弱者のために」と平気で口にできる人たちはもっと嫌いです。「弱者」といえる人は、相対的に自分が「強者」となります。そして「弱者のために」という言葉は、持てる者が持たざる者に施しを与えているような印象があります。「弱者」という言葉を使う人の多くは、そのことを自覚していません。「パンがなければケーキを食べればいいでしょ」のマリー・アントワネットの有名なフレーズを連想します。
でも、大都市圏に暮らす人以外にとって、自家用車を運転できない人は、間違いなく「弱者」です。障害者、お年寄り、病人、けが人、子ども、低所得者……。彼ら彼女らは(そして私も)、「交通弱者」です。
購買行動も、ロードサイドにある量販店しかない状況だと非常に困ります。電化製品や安い衣類などは通販でもなんとかなりますが、我が家でいちばん困ったのが、ストーブの灯油でした。20リットルのポリタンクを自転車の荷台にくくり付けるのは不可能ですし、何より危険です。
雇用も変わってきます。今度オープンする大規模なショッピングセンターの従業員募集の広告が新聞によく出ています。そこには、大きな駐車場があって、自動車通勤もできることが書かれています。逆に言えば、車がなければ働けません。運転できない人にとっては、雇用機会すら狭められます。
「交通弱者」は「経済的弱者」や「文化的弱者」と重なります。そして「社会的弱者」に連なります。
これは当地だけでなく、日本中で見られる光景です。昨年、仕事の関係で隣の浜松の市長にお会いしましたが、同席していた女性が、「くるくるバス(浜松のコミュニティバス「くるる」のこと)をもっと増やしてください」と、悲痛な声で懇願していました。
同様のバスは当地にもあります。一時間に一本、それも一方通行という不便極まりないものです。口の悪い知人は「年寄りしか乗ってないユーバス(当地のコミュニティバスの愛称)」なんて言っていましたが、それでも病院通いをするようになり、私も時折利用するようになり、お年寄りにとっては数少ない貴重な足なのだと痛感しました。
しかし、問題の本質はそこにはありません。
どうして車がなくては何もできない社会になってしまったのかは、新自由主義社会の推し進めた規制緩和に原因があります。小泉―竹中路線がその流れに棹を差しました。当時の小泉首相は、「痛みをともなう改革」の言葉で国民に我慢を強いました。それはそれで評価できるところもあります。
最大の問題は、真っ先にひどい「痛み」を感じる人が、声を上げることもできない「弱者」だったことです。
交通・都市の問題を論じてきましたが、今日の日本社会のどの分野にでも当てはまることです。私に直近のことだと、医療、福祉、介護、教育、雇用、労働、社会保障、地域社会の崩壊、などなど。副次的効果や潜在的逆機能はもっと多くあります。
この大きすぎる問題に私個人ができることはほとんどありません。せめて、職場や家庭など現場で少しでも改善させていくことしかできません。
ですから、ひとりひとりの有権者が、意欲と能力を持った代表者を責任を持って選び、送り出すことが重要だと思っています。
当地の選挙に立候補した候補者のうち、ブログを持っている方に、今回の文章をトラックバックで送ってみようと思っています。
送られたほうは迷惑でしょうし、そんなことやっても何も変わらないという人もいるでしょうが、何もやらずに不平不満を言うよりは幾分マシだとも思います。
それに、候補者の方々も、そして、今、このブログを見ているあなただって、まるっきり人ごとではないのですから。だって、誰もが年を取るのですから。年を取るってことは、障害者になるってことですから。あるいは不慮の事故や病気や災害で身体の機能を損傷することだって、誰にだって可能性はあるのですから。
そのときになって「車がないと何もできない社会にしやがって」と憤っても遅いですからね。
磐田市長・市議会議員選挙の投票日は4月19日(日曜日)です。
(追記・4月14日)
候補者の方でブログどころかHP持っている人が圧倒的に少なかったorz。
TB受け取った方、トラックバックスパムのように思われるかもしれませんが、そのときには遠慮なく削除してください。
送れなかった候補者の方、無視したわけではありませんのでどうかご容赦ください。